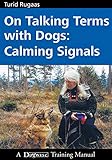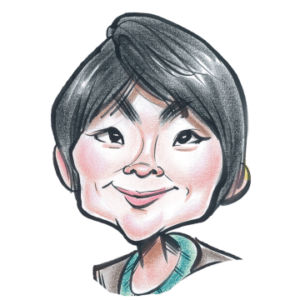伏せる(Lying down like the Sphinx)
- 相手を落ちかつかせるための最上級のシグナル
- 「座る」より意味合いが強い
- ほかのボディランゲージと総合して判断した場合、攻撃を表すこともあるので注意
はじめに:「フセ」はただのコマンドではない
犬の「フセ」という行動は、多くのしつけ教室やパピークラスで基本動作として教えられることが一般的です。
しかし、犬にとってこの「フセ」は単なる服従の姿勢ではなく、相手との関係を円滑にするための大切な“言葉”として機能している場合があります。
「フセ」はカーミングシグナル(=相手を落ち着かせるためのサイン)として使われることもあるのです。
この記事では、犬たちの「フセ」が持つ本来の意味と、それをコマンドとして強制することがなぜ問題なのかを丁寧に解説し、愛犬とより深くつながるためのヒントをお届けします。
カーミングシグナルとは?
犬たちは人のような言葉ではなく「ボディランゲージ」を使って自身の感情や意図を伝えます。
なかでもとくに注目されているのが「カーミングシグナル」(calming signals)と呼ばれる一群の動作です。
これはノルウェーのドッグトレーナー、トゥーリッド・ルガース(Turid Rugaas)氏によって提唱された概念で、犬たちが他者との緊張を和らげるために見せる行動のことです。
犬同士だけでなく人間や他の動物に対しても使われる、いわば「平和のサイン」です。
代表的なカーミングシグナルには、「あくび」「目をそらす」「身体を横に向ける」「地面の匂いを嗅ぐ」などがあります。
「フセ」はその中でも犬がとくに強いメッセージを送りたいときに表すカーミングシグナルの一つです。

「フセ」が意味するもの
犬が前足を伸ばし、お腹を地面につける伏せの姿勢の「フセ」。
「フセ」と聞くと多くの人が「コマンドとして教えるもの」と思いがちです。とくに「フセ」は犬の服従心を育てるとされ、しつけ本やパピークラスでも必須課題の一つとされる服従訓練のひとつです。
しかし、本来「フセ」は犬が自発的に発する重要なカーミングシグナルです。
「フセ」は相手に「敵意はないよ」「落ち着いているよ」というメッセージを届けるための「犬の言葉」です。
つまり、これは単なる服従姿勢ではなく自ら発信する“気持ちの表現”なのです。
だからこそ、これを人間が一方的に「コマンド」として強制してしまうと、犬が持っている本来のコミュニケーション手段を奪ってしまう危険があります。
「フセ」がカーミングシグナルとして使われる場面
シーン1:初対面の犬と出会ったとき
見知らぬ犬と出会った場面で、そっと伏せる行動が見られることがあります。
これは「自分は穏やかだよ」「争うつもりはないよ」と伝えて、相手の警戒を和らげようとするメッセージかもしれません。
シーン2:初めての場所で緊張しているとき
慣れない環境に置かれたとき、犬が突然フセをすることがあります。
これは不安や警戒の表れであり、その場を観察しながら気持ちを落ち着かせようとしている可能性があります。
シーン3:叱られた後の態度として
飼い主に叱られてフセをする犬もいます。
このときのフセは、「もう争いたくない」「落ち着きたい」という意思表示かもしれません。

カーミングシグナルではない場合も…
また、じつは「フセ=必ずしも穏やかな気持ち」とは限りません。
たとえば、一部の和犬や猟犬タイプの犬種では「フセ」が攻撃の準備姿勢であることがあります。
「遠くにいる犬を見て伏せ、相手が近づいた瞬間に飛びかかる」ときの「フセ」は、緊張と警戒、そして攻撃の意図を含んでいます。
つまり「伏せているから大丈夫」と単純に判断せず、犬の表情、目線、体の硬さ、耳や尾の様子など、全体のボディランゲージを総合的に読み取ることが必要です。

-350x350.png)
-1-350x350.png)
愛犬がフセをしたとき、どう接するべき?
フセという行動には様々な意味が含まれています。犬の気持ちを読み取り、状況に合った対応を心がけましょう。
以下のように対応すると、犬の安心感を高めることができます。
きっかけを確認する
他の犬や人の接近がフセの原因になっていないか、周囲の状況をチェックしましょう。
攻撃か平和かの判断
そのフセの理由は攻撃と平和のどちらの意図をもって出されたものかを判断します。
フセをしている他犬に遭遇したら
フセの姿勢でいる他犬と遭遇したときも、油断せず冷静に対応することが大切です。
むやみに近づかない
フセの姿勢が緊張や攻撃の予兆であることもあるため、距離を保って観察しましょう。
見た目に惑わされない
「リラックスしているように見えるから安心」と決めつけず、尾の振り方、筋肉の緊張、目線などをチェックしましょう。
自分の犬への配慮も忘れずに
愛犬が不安を感じている様子なら、無理にその場にいさせず、相手の犬を刺激しない「カーミングシグナル」を出させるように飼い主がサポートします。
:カーミング・シグナル(3)-350x350.png)
:カーミング・シグナル(1)-350x350.png)
「しつけ」としてのフセの再考
もちろん、「フセ」のコマンドを教えることが完全に悪いというわけではありません。
愛犬から言葉を奪うかも?
しかし、飼い主がカーミングシグナルとしての「フセ」の意味を知らずに、単なる服従訓練の一環としてコマンドで伏せるように教えてしまうと、愛犬は大事な「犬の言葉」をひとつ失うことになります。
自分の気持ちを表現をする手段がなく、混乱やストレスの原因にもなり得ます。
オスワリで十分かも
愛犬が気持ちを落ち着けるのを手助けするための手段としては「オスワリ」を教えるだけでも十分です。

もし、どうしても「フセ」を教えたいのであれば、犬が自然とその姿勢をとる状況や気持ちを尊重することが大切です。
あくまで、信頼関係の中で「落ち着いた状態を共有するための合図」として扱うことを意識しましょう。

まとめ:犬の「言葉」に耳を傾けよう
「伏せる」(Lying down like the Sphinx)は、犬が自らの心を整え、他者と平和に接したいと願うときに見せる大切なカーミングシグナルです。
これを単なる「訓練種目」として捉えるのではなく、犬からの“言葉”として受け取ることで愛犬とより深い信頼関係を築くことができます。
愛犬が自発的に「フセ」をしたとき飼い主はまずその意図を読み取り、愛犬がその場に応じた適切なふるまいをすることができるよう配慮してみましょう。
【一覧表】カーミングシグナル全30種
犬たちのボディランゲージのなかにカーミングシグナルに該当するしぐさは30種類あると言われます。
愛犬がよく見せる行動や、お散歩中に見かけて意味を知りたかった行動をクリックしてゼヒ読んでくださいね。
犬の「本当の気持ち」が分かるようになると愛犬との暮らしがもっと楽しくなりますよ!
- 【完全版】カーミング・シグナルをおぼえよう!
- ゆっくりと歩く(Walking slowly):カーミング・シグナル(1)
- 身体を横に反らす(Turning the side):カーミング・シグナル(2)
- カーブを描きながら近づく(Walking in a curve):カーミング・シグナル(3)
- 横を見る(See the side):カーミング・シグナル(4)
- 尻尾を振る(Wagging tail):カーミング・シグナル(5)
- 座る(Sitting down):カーミングシグナル(6)
- どこかに行ってしまう(Go away):カーミング・シグナル(7)
- 前足を上げる(Lifting ones paws):カーミングシグナル(8)
- 鼻を持ち上げる(Nose up):カーミングシグナル(9)
- 2頭のあいだを裂く(Going between, splitting up):カーミング・シグナル(10)
- あくびをする(Yawning):カーミングシグナル(11)
- 身体を振る(Shaking off):カーミングシグナル(12)
- 身体を低い位置に落とす(Lower the body):カーミングシグナル(13)
- 遊びの誘い(Going down in play position/ Play Bow):カーミングシグナル(14)
- 子犬のように振る舞う(Like a puppy):カーミングシグナル(15)
- そっぽを向く・頭を動かす(Turning the head):カーミングシグナル(16)
- 口元を後ろへ引く (Lengthen the corner):カーミング・シグナル(17)
- 歯をカチカチと鳴らす(Tang the teeth):カーミング・シグナル(18)
- 口と鼻の周りをなめる(Licking nose):カーミング・シグナル(19)
- 口をパクパクさせる(Gasp the mouth):カーミング・シグナル(20)
- 背中を向ける(Turning the back):カーミング・シグナル(21)
- おしっこをする(Peeing):カーミング・シグナル(22)
- その場所にいないように振る舞う(Acting like nothing happen):カーミング・シグナル(23)
- 静止(Freeze):カーミング・シグナル(24)
- 地面の臭いを嗅ぐ(Sniffing the ground):カーミング・シグナル(25)
- 伏せる(Lying down like the Sphinx):カーミング・シグナル(26)
- 顔の向きを変える(Turn the face around):カーミングシグナル(27)
- 目をそらす(Gaze Aversion):カーミングシグナル(28)
- 笑う(Smiling):カーミングシグナル(29)
- 転移行動(Re-directional behavior):カーミング・シグナル(30)
あなたにピッタリの情報かも?

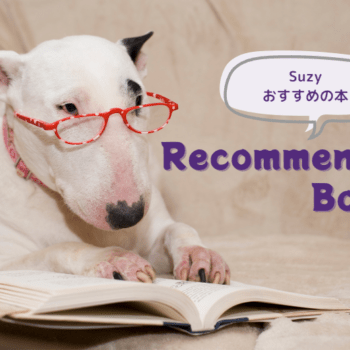

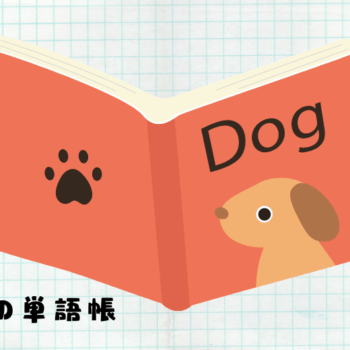

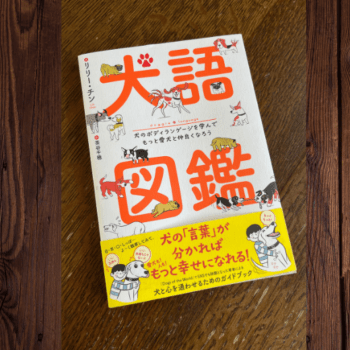
SuzyにLINEで質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。


:カーミング・シグナル(26).png)