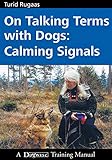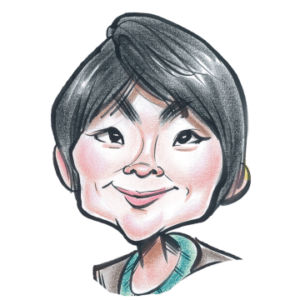Yawning
- 自分と相手の緊張をほぐす行為
- ボディランゲージの「口」の項参照
カーミング・シグナルとは
犬たちはほかの犬や人とのコミュニケーションにおいて視覚的・身体的なサインであるボディランゲージを通じて自らの感情や意図を伝える能力を持っています。
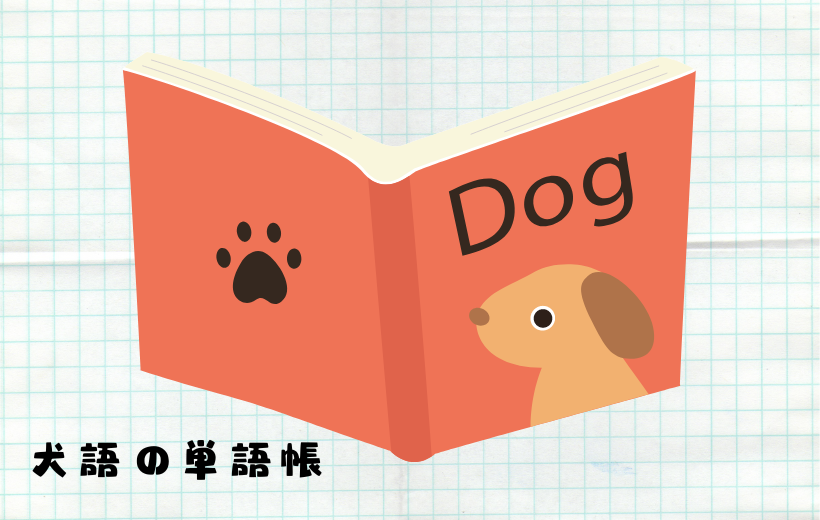
犬たちは自分の感情や意思を表すため犬に対しても人に対しても、さまざまなボディランゲージ(含むカーミング・シグナル)を用いて犬ならではのコミュニケーションをしています。身体の複数のパーツを同時に使い、その組み合わせによって複雑な感情を表現しています。また、その感情は瞬時に刻々と変化して...
ボディランゲージの一種
そのひとつが「カーミングシグナル」(calming signals)と呼ばれるボディランゲージです。
カーミングシグナルは他者とコミュニケーションを図るために犬たちが使う自然なボディランゲージで自分や相手を落ち着かせるための「平和のサイン」です。
ノルウェーのドッグトレーナーであるTurid Rugaas(トゥーリッド・ルガース)氏により犬のボディランゲージのうち27~30種類が「カーミングシグナル」であると定義されました。
このカーミングシグナルは犬の行動学において重要な要素とされています。
平和のサイン
カーミングシグナルはおもに犬がストレスを感じた時や緊張状態にあるとき、自分や相手の感情を落ち着かせるために使用されます。
緊張状態を軽減し相手との衝突を避けるために使われるボディランゲージの一種です。
犬同士のあいだのみならず飼い主を含む人間や犬以外の動物に対してもこのカーミングシグナルを通じて平和的なコミュニケーションを試みます。
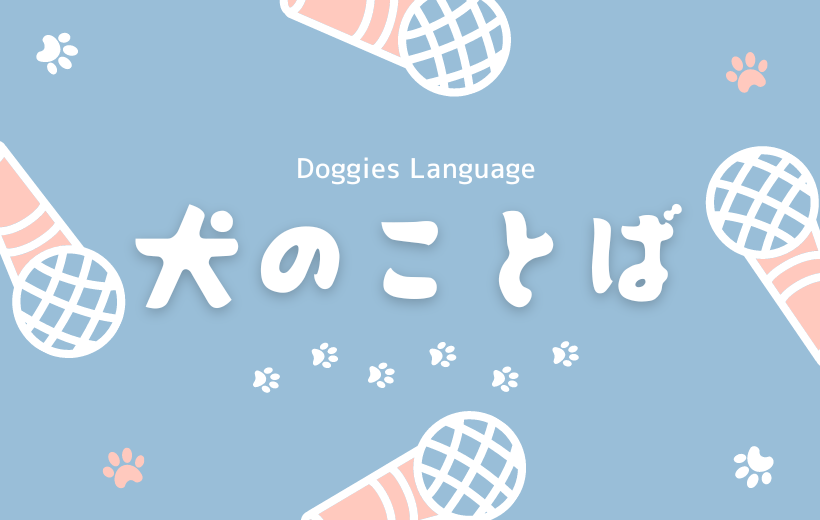
犬が身体で自分の気持ちを表す「ボディーランゲージ」のなかには「カーミングシグナル」と呼ばれるカテゴリがあります。 これは犬社会を円滑にするためのとても重要なボディーランゲージになっています。 カーミング・シグナルとは? ノルウェーのドッグトレーナーであるTurid Rugaas(トゥーリッ...
犬が「あくびをする」理由
犬が「あくびをする」のは必ずしも眠気や疲れていることが理由とは限りません。
犬があくびをする理由としては以下のような複数の理由が考えられます。
- 頭をリフレッシュさせるため
- 自分の緊張やストレスを解消したいとき
- 相手に落ち着いてほしいとき
1)頭をリフレッシュさせるため
あくびは脳に酸素を送り活性化するための自然な反応です。
単に眠たいから
とくに寝る時間帯や目が覚めたばかりのときにするあくびは脳に酸素を送るためであると考えられます。
「あくび」と聞いて私たちが一番最初に思いつく理由です。
退屈・気分転換
犬は退屈しているときにも「あくびをする」ことがあります。
これも眠たいときと同じ理由でするあくびです。
脳に酸素を送り頭をリフレッシュさせるための普通のあくびです。
2)自分の緊張やストレスを解消したいとき
犬も「あくびをする」と神経系がリラックスモードに入りやすいとされています。
犬たちは緊張を感じたとき「あくびをする」ことで自分を落ち着かせようとします。
たとえば、
- 見知らぬ犬や人と対面したとき
- 知らない場所へ行ったとき
- どうしたらよいか分からずに困っている(言われたことが分からない)とき
- 嫌なことを我慢している(診察など)とき
などに見られるあくびはカーミングシグナルに相当します。
あくびによって深い呼吸をすることで心が落ち着き安心感を得ることができるからです。
この投稿をInstagramで見る
3)相手に落ち着いてほしいとき
犬は「あくび」を使ってほかの犬や人に「敵意はない」「落ち着こう」という意図を伝えようとしていることもあります。
たとえば、
- 自分の近くにいる犬が興奮しているとき
- 飼い主が叱ったり強い口調で話しているとき
などに見られることがあります。
このような状況で見せるあくびは相手をリラックスさせ場の緊張をほぐすためのメッセージとなります。
このように犬たちの「あくび」には私たち人間が想像もしない大切な意味が含まれています。
この投稿をInstagramで見る
飼い主のとるべき対応
愛犬があくびをしているのを見つけたら、飼い主はどのように対応すればよいでしょうか。
あくびの理由を探る
先に挙げたとおり、犬があくびをする理由はさまざまです。
- 頭をリフレッシュさせるため
- 自分の緊張やストレスを解消したいとき
- 相手に落ち着いてほしいとき
のどれに該当するかを状況を踏まえて推測します。
眠たそうだったら
眠たいのにテンションを上げるような遊び(ボール投げや引っ張りっこなど)に誘ってしまうと犬は疲れを取ることができません。
眠たいときはハウスやクレートに入るように促して、落ち着いて眠ることができるようにしましょう。
もちろん、眠っている犬をからかって起こすようなことは決してしてはいけません。
退屈していたら
反対に退屈が原因であくびが出たのなら元気の出る遊びやお散歩に誘いましょう。
あくびをし返す
愛犬が自分の緊張やストレスを解消しようと思ってあくびをしているときは、緊張をほぐす手助けをしてあげます。
その際、効果的な方法は飼い主があくびをして見せることです。
犬たちはカーミングシグナルを「自分がリラックスするため」と「相手をリラックスさせるため」に使います。
このため、私たち人間が犬に対してあくびをして見せることによっても緊張をほぐしてリラックスを促す効果があります。
声掛けは内容次第
愛犬の緊張をほぐすために声をかける飼い主さんは多いです。
しかし、その内容が逆効果であるケースが非常に多く「諸刃の剣」となっています。
ヘタな声かけはかえって緊張を高めてしまうためSuzyは声を使わない方法を強くお勧めします。
見守る&褒める
愛犬が自分の近くにいる興奮した犬を落ち着かせたくて眠たくないのにあくびを連発することがあります。
これは精神的に不安定になっている仲間を助けようとする行為です。
他者に配慮できる器の大きな子です。
「偉かったね」と優しく褒めてあげるべきことです。
まとめ:理解と対応
犬が「あくびをする」というカーミングシグナルは自分の緊張や不安、相手に対して敵意がないことを伝えるために使われる大切なボディランゲージ(犬語)です。
愛犬がカーミングシグナルを出しているとき飼い主は愛犬の気持ちを尊重した対応をすることが求められます。
また、ほかの犬がこちらに対してこのシグナルを使ってきたときも相手の犬の気持ちを尊重した対応をすることが大切です。
犬のカーミングシグナルを正しく読み取るスキルを身につけて、日常生活のなかでこうしたサインに気づき、犬の気持ちに寄り添うことが愛犬とのより良いパートナーシップの構築につながります。
カーミングシグナル全30種
このほかにもたくさんのカーミングシグナルがあります。
愛犬がよく見せる行動や、意味を知りたい行動からクリックして読んでくださいね。
- ゆっくりと歩く(Walking slowly):カーミング・シグナル(1)
- 体を横に反らす(Turning the side):カーミング・シグナル(2)
- カーブを描きながら近づく(Walking in a curve):カーミング・シグナル(3)
- 横を見る(See the side):カーミング・シグナル(4)
- 尻尾を振る(Wagging tail):カーミング・シグナル(5)
- 座る(Sitting down):カーミングシグナル(6)
- どこかに行ってしまう(Go away):カーミング・シグナル(7)
- 前足を上げる(Lifting ones paws):カーミングシグナル(8)
- 鼻を持ち上げる(Nose up):カーミングシグナル(9)
- 2頭のあいだを裂く(Going between, splitting up):カーミング・シグナル(10)
- あくびをする(Yawning):カーミングシグナル(11)←このページ
- 体を振る(Shaking off):カーミングシグナル(12)
- 身体を低い位置に落とす(Lower the body):カーミングシグナル(13)
- 遊びの誘い(Going down in play position/ Play Bow):カーミングシグナル(14)
- 子犬のように振る舞う(Like a puppy):カーミングシグナル(15)
- そっぽを向く・頭を動かす(Turning the head):カーミングシグナル(16)
- 口元を後ろへ引く (Lengthen the corner):カーミング・シグナル(17)
- 歯をカチカチと鳴らす(Tang the teeth):カーミング・シグナル(18)
- 口と鼻の周りをなめる(Licking nose):カーミング・シグナル(19)
- 口をパクパクさせる(Gasp the mouth):カーミング・シグナル(20)
- 背中を向ける(Turning the back):カーミング・シグナル(21)
- おしっこをする(Peeing):カーミング・シグナル(22)
- その場所にいないように振る舞う(Acting like nothing happen):カーミング・シグナル(23)
- 静止(Freeze):カーミング・シグナル(24)
- 地面の臭いを嗅ぐ(Sniffing the ground):カーミング・シグナル(25)
- 伏せる(Lying down like the Sphinx):カーミング・シグナル(26)
- 顔の向きを変える(Turn the face around):カーミングシグナル(27)
- 目をそらす(Gaze Aversion):カーミングシグナル(28)
- 笑う(Smiling):カーミングシグナル(29)
- 転移行動(Re-directional behavior):カーミング・シグナル(30)
関連記事
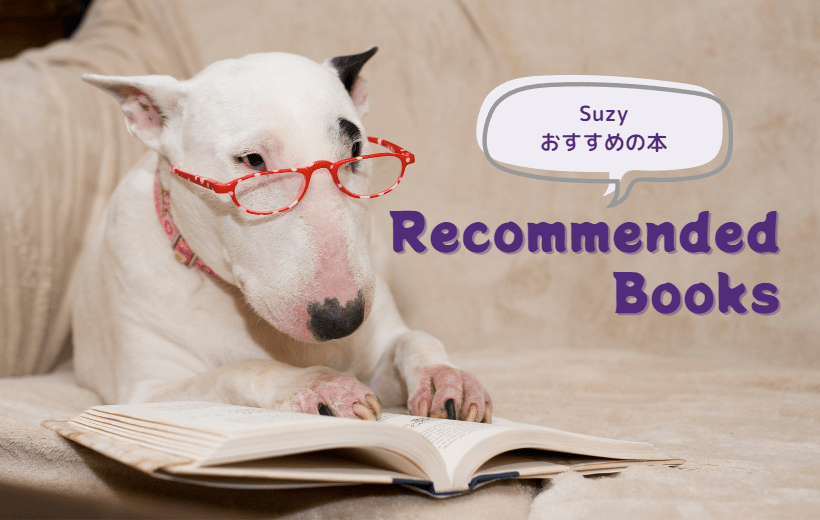
犬との暮らしについてもっと知識を得たいとき、もっと知りたいことがあるとき、本を読むことも大切です。 ドッグトレーナーが必読を勧める2冊 Suzyが絶対に読んでほしい本は以下の2冊です。発行年は古いものもありますが、内容はまったく古くありません。「犬のしつけ」の名著です。 1冊目...
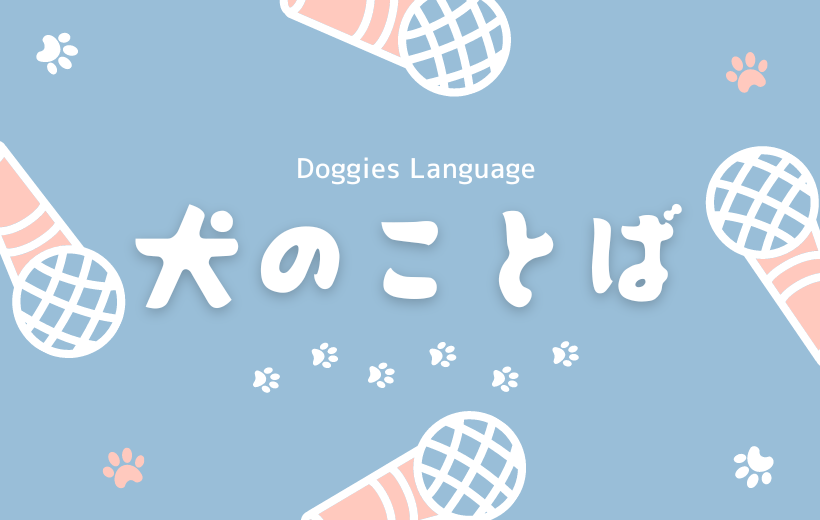
犬たちには「犬のことば」があるということはすでにご存じかと思いますが、ここで改めて犬たちのことば「犬語」についてまとめてみたいと思います。 犬の言葉は世界共通! 私たち人間の世界では国によって使う言語が異なり、ほかの国へ行くと翻訳ツールがなければさっぱり言葉が通じません。それどころかこん...
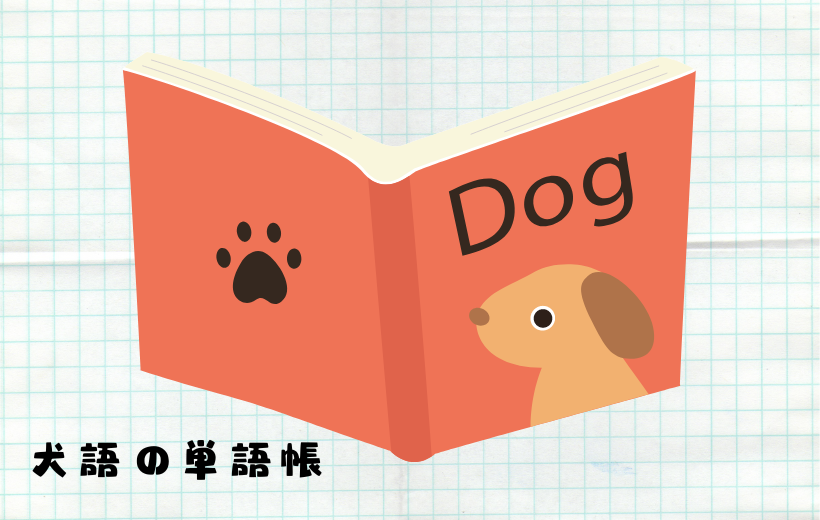
犬たちは自分の感情や意思を表すため犬に対しても人に対しても、さまざまなボディランゲージ(含むカーミング・シグナル)を用いて犬ならではのコミュニケーションをしています。身体の複数のパーツを同時に使い、その組み合わせによって複雑な感情を表現しています。また、その感情は瞬時に刻々と変化して...
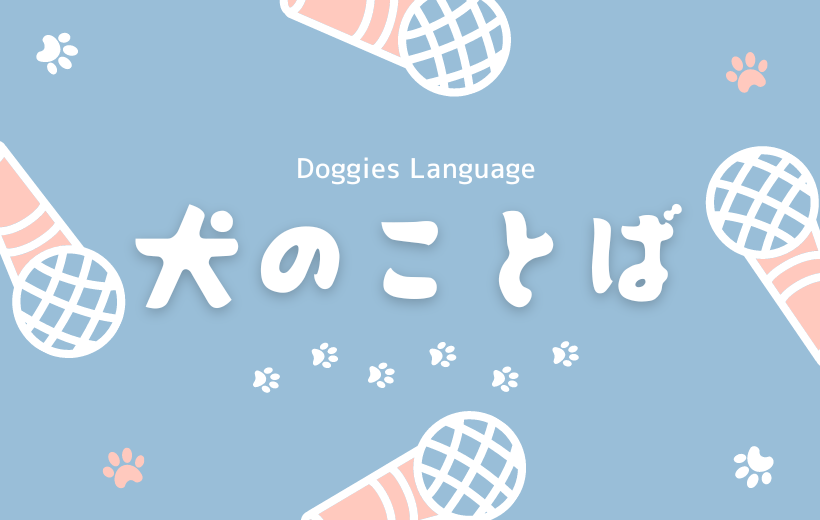
犬たちは日本語を話しませんが、犬のことばをもっています。犬とともに暮らす人は、犬のことばを学びましょう。犬の気もちを読み取るスキルを身に付けさえすれば、心のボタンを掛け違えることはなくなります。そして、飼い主か愛犬のどちらか一方だけがガマンを強いられることのない、イヌ・ヒトの...
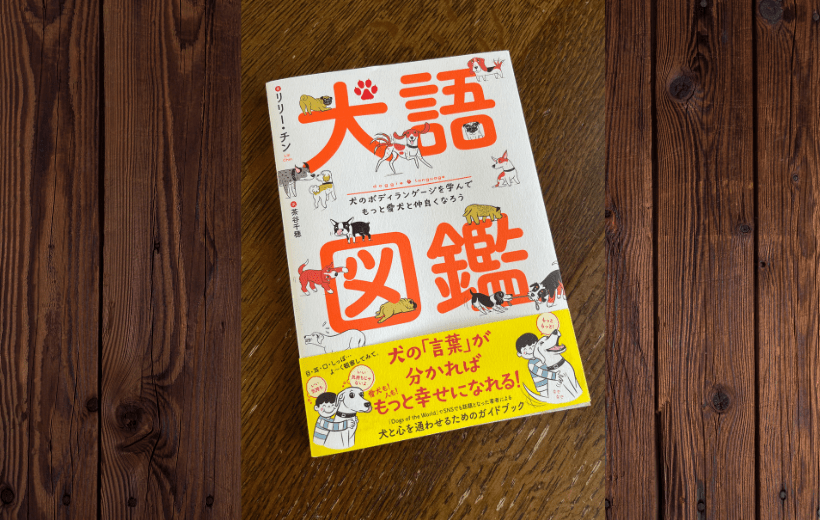
PALのレッスン等で飼い主さんに配布している『犬語』のリーフレットは、ニューヨーク在住のイラストレーターLili Chinさんが無償配布している「犬のボディランゲージ」のイラストです。『犬語図鑑:犬のボディランゲージを学んでもっと愛犬と仲良くなろう』 これをより詳しく掘り下げた本が、日...
LINEでSuzyに質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。
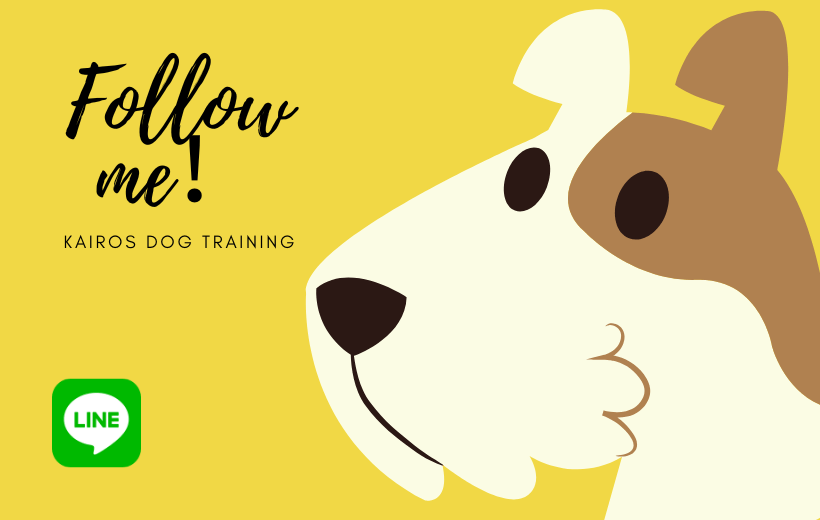
Suzyに聞きたい! 犬のしつけ情報を探してインターネットをしていてこのサイトにたどり着き、いろいろな記事を読んでみて、もっと知りたいと思うことがあったかもしれません。そんなときは、LINEお友達登録のうえ、チャットでご質問をお送りください。 質問受付中 誰かが知りたいと思っていること...

:カーミングシグナル(11).png)