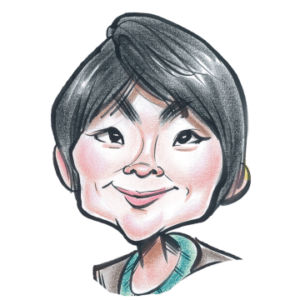Dog Year
という言葉があります。
イヌはヒトよりもうんと早く歳をとり寿命を迎えるので、ものすごく(時間の)スピードが速いことをさしてこのように表現します。
How Old Is My Dog? Identification of Rational Age Groupings in Pet Dogs Based Upon Normative Age-Linked Processes
行動と認知の面からみた犬と人間の年齢の比較にかんして「Frontiers in Veterinary Science 」Vol. 8において新しい研究結果がでたそうです。

Behavioural development is a lifelong process where cognitive traits such as learning, and memory may be expected to take a quadratic or linear trajectories....
行動と認知の面からみた犬と人間の年齢の比較
- 子犬期:0〜6カ月
- 思春期:6〜12カ月
- 若年成犬期:12〜24カ月
- 成犬期:2〜6歳
- シニア期:7〜11歳
- 高齢期:12歳以上
さらにシニア期を細かく分類すると、
- シニア前期:7〜9歳
- シニア後期:10〜11歳
- 高齢期:12〜14歳
- 超高齢期:15歳以上
というふうに分類するのがよいと説明しています。
大型犬と小型犬での年齢の差はない
また、この研究では大型犬と小型犬での年齢の差はないとしています。
大型犬が小型犬より短命なのは大型犬が早く歳をとるのではなく大型犬種が遺伝的に若死にするように作られているのだと論じています。
大型犬は小型犬より早く寿命を迎えますが同じ年齢の小型犬と比べて認知機能が劣るということはないのだそうです。
これは、わかりやすくてとても良い説だと思いました。
これからは犬の大きさに関係なくシンプルに年齢換算できます。
犬の年齢を人の年齢に置き換えたら?
以下はSuzyのこれまでのトレーナーとしての経験値から想定する「犬=人」の年齢換算です。
犬たちは人間の何倍ものスピードで大人になり歳をとっていきますが、そのスピードは一定ではありません。
ライフサイクルにおいてキーポイントとなるステージがいくつか存在しています。
- 子犬期(~5カ月くらいまで)
- 思春期・若犬期(生後6カ月~2歳くらい)
- 成犬期(2〜6歳くらい)
- シニア前期(7〜9歳)
- シニア後期(10~11歳)
- 高齢期(12〜14歳)
- 超高齢期:15歳以上
1)子犬期(~5カ月くらいまで)
犬は最初の1年間で人の約15年分に相当する成長を遂げます。
たったの1カ月が1年以上に相当します。
このため子犬を飼う人はあらかじめ犬の月齢と人間の年齢の比較を頭に入れておく必要があります。
生後2カ月は人間の1歳くらい
「動物の愛護および管理にかんする法律」(動愛法)により生後8週齢に満たない子犬の販売は禁止されています。
このため一般の飼い主の元へ子犬がやってくるのは生後56日以降となります。
人間に置き換えると卒乳を始めた1歳前後といったところです。
生後3カ月は幼稚園生
生後3カ月は「未就学児」として考えると良いです。
まだ、我慢できる時間も限られます。
教えるべきはトイレくらいです。
この時期に根を詰めて訓練しても後で忘れます。
生後4カ月は小学1・2年生
乳歯が抜けてほとんどの歯が生え変わるのが生後4カ月。
だいたい、小学校低学年くらいになったとイメージすればよいでしょう。
ワクチンが終わってほとんどの子がお散歩デビューする時期です。
生後5カ月は小学3・4年生
精神年齢が大きく分かれてくる時期です。
幼い子はまだ「幼い」ですが、早熟なコはそろそろ「思春期」に差し掛かります。
和犬は精神的に早熟な傾向
なお、柴犬をはじめとした和犬犬種は1カ月くらい前倒しで考えると良いです。
生後4カ月から「思春期」が始まることが多いです。

柴犬(しばいぬ「しばけん」ではありません)。 ブームが始まったのは、どのくらい前だったでしょうか…。 2010年あたりから、しつけ教室にやってくる犬種の割合として柴犬がだんだん増えてきました。 つぶやきときどき、秋田犬や四国犬、甲斐犬なんかも来ますよ。 柴犬ブームがやってきた JKCの犬種...
2)思春期・若犬期(生後6カ月~2歳くらい)
この期間は犬にとってさまざまなことを学ばなければならないとても重要な時期です。
生後6~7カ月は小学5・6年生
人間に置き換えると小学校高学年にあたる時期。
この頃から、これまでとは大きくものの考え方が変わってきます。
しつけの内容を成犬用のものに切り替えていく時期です。
生後8~12カ月は中高生
子犬のときに通用したやり方が通じなくなり飼い主さんがもっとも混乱し始める時期です。
身体も心も成熟して、大人になるためのしつけを理解することができるようになっています。
集中力や自制心を身につけることを中心にしつけに取り組みます。
1歳半(18カ月)は新社会人
人間の飼い主は1歳はまだ赤ちゃんだと思っている人がとても多いですが、もう立派な成人です。
周りの犬は1歳過ぎた犬のことは「成犬」とみなします。
飼い主がいつまでも子犬扱いしていると愛犬は心を病みます。
3)成犬期(2〜6歳くらい)
早い子では2歳を迎えるあたりで「性格」が定まってきます。
しかし、2歳頃から「遅れてやってきた思春期」が始まる子もときどきいます。
2~3歳は20代
心身ともに充実してくるのが2~3歳くらいです。
2~3歳くらいの成犬でもともと相性があう(活動レベルが家族と同じくらい)の犬を飼い始めるとスムーズに家庭に馴染むことができます。
まだまだ体力がたくさんある年齢なので、愛犬と毎日たくさんお散歩したり、アクティブに活動したい方は、すでにこの年齢まで育ち済みの犬を迎えることをお勧めします。

犬と一口に言っても、選ぶときに考慮すべき項目がたくさんあります。 子犬か成犬か? 初めて犬を飼うときイメージするのはまず「子犬」でしょう。ですが、子犬を一から育てることには、多大な時間と労力を要します。まだ、心も体も未発達のため、どのように育つかは、すべて飼い主の接し方と与えた環...
4~6歳は30代
より、落ち着きが出てくる年齢です。
個体によりますが、これまでよりも運動欲求が減ってくる年齢です。
たとえば、これまで毎日朝晩1時間以上散歩に行き、走ったりボール投げなどをして体力を発散させなければ、家のなかで吠えたりイタズラが激しかったような犬であっても、走らない30分零度のお散歩でも満足できるようになるなどしてきます。
このため、夫婦でフルタイムの共働きで朝晩に1時間も散歩をする時間をとれない家で犬を飼いたいと考える人は、この年齢の犬をお迎えするとスムーズに家庭に馴染みやすいです。
もちろん、休日は一緒にお出かけすることも十分楽しめます。
4)シニア前期(7〜9歳)
医療や食が向上した結果、家庭で暮らしている犬たちの多くが長生きするようになり犬生の大半が「シニア期」となっています。
7歳は犬の厄年=人の40代に突入!
血液検査などの健康診断をすると老化現象が見られはじめるのが一般的に「7歳」と言われます。
今まで健康優良児だった愛犬に初めて「病気」が発覚するのも「7歳」が多い傾向にあります。
このため犬の7歳は「犬の厄年」と呼ばれます。
見かけは元気そのもので今までの愛犬と何も変わらないのですが、少しずつ「老い」がはじまってくる時期です。
しつけの見直し時期
今後、病気の治療のために「投薬」が必要になったり、頻回に病院通いをすることになっていきます。
そのとき、過剰に犬が負担を感じてしまうようでは「長生き」は見込めません。
このため、診察や投薬、もしくは入院などに対して愛犬が過剰に負担を感じることがないような「しつけ」を予めしていく必要があります。

保定とは? 「保定」とは、人間が犬の身体を抱きかかえて犬が自由に身動きを取れないようにすることです。この保定ができることは、犬のしつけ3原則の「愛犬の命と健康を守る」を実践するために、まず最初にできるようにすべきことです。どんなときに使うの? 動物病院で診察や処置を受ける際、動か...

愛犬の命と健康を守るため 首輪やリードを着けられなければ、お散歩に連れていくこともできません。動物病院の診察台の上でじっとしていられなければ、病気を見逃すこともあります。また、飼い主が口に手を入れることを嫌がったまま病気になると、お薬をきちんと服用できず、助かる命も助かりません。 ...

愛犬にしつけをする第1の目的は、ずばり「愛犬の命と健康を守るため」です。これをお話すると、「ソンナノ、アタリマエジャン…」と、拍子抜けされる飼い主さんがほとんどです。ですが、その飼い主さんが「愛犬の命を守るしつけ」が、ちゃんとできているかというと、そうじゃなかったりします。た...
全身麻酔の処置をする最後のチャンス
避妊手術をしていないメスは「乳腺腫瘍」にかかるリスクが高まります。
まだ体力がある若いころに「麻酔をかけるなんて可哀そう」という理由で「避妊手術」をしなかったために10歳を超えてから命がけで全身麻酔をして「乳腺腫瘍」の手術をする飼い主さんは少なくありません。
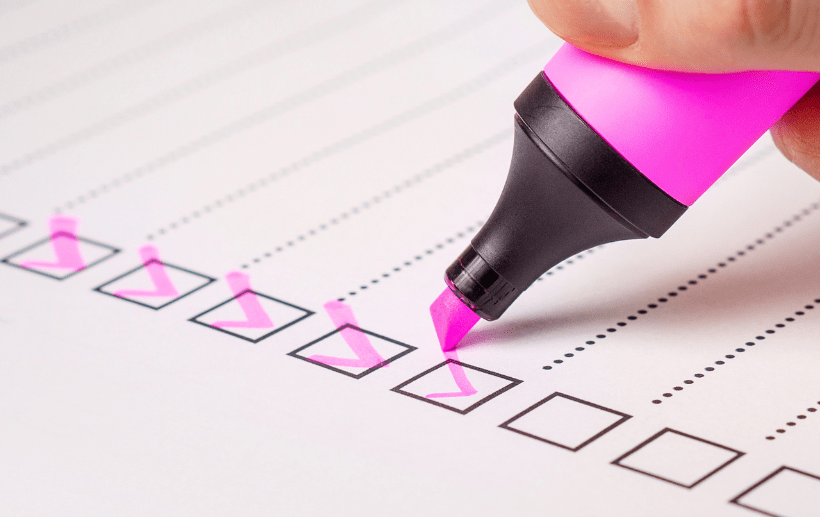
大好きな愛犬のために良かれと思って飼い主がしていることが、実は愛犬を苦しめていることがあります。その一つに「犬の擬人化」があります。犬は「犬」という人間とは違う生き物でありながら、人間の社会で共に生活を送っているため、われわれはつい人間と同一視してしまいがちです。あなたは愛犬...
死因に直結する「歯周病」
歯石の除去には全身麻酔が必要です。
歯みがきをきちんとやっていても奥歯にどうしても歯石が溜まってしまうこともあります。
歯石が原因となって罹患する歯周病ですが、この歯周病菌が「心臓病」や「糖尿病」の一因であることは犬の飼い主にあまり知られていません。
全身麻酔のリスクが一段と高まるシニア期になる前までが予防医療での全身麻酔の最後のチャンスであるともいえます。
5)シニア後期(10~11歳)
気持ちはまだまだ若いですが身体の老いが目に見えてくるのが10歳あたりからです。
10歳は犬の還暦=60代に突入!
黒い子でなくとも白髪が目立ってきたり毛のボリュームが減ってきたことが見た目で分かるようになってきます。
また、暑さ・寒さに弱くなってきたりジャンプ力が明らかに落ちたのを飼い主が実感するタイミングです。
これまでは健康診断の結果以外で愛犬の「老い」を感じることがなかった飼い主も客観的に老いを実感しはじめる時期といえます。
超大型犬や短頭種などもともと寿命の短い犬種では寿命を迎える子も出てきます。

元気なうちから考えたくないことではありますが、イヌは人の5倍の速さで歳を取り飼い主より先に寿命を迎える運命にあります。飼い主が先に亡くなることのほうがイヌにとって辛いことであり愛犬を看取ることは飼い主の最大の責任です。愛犬が亡くなった後も葬儀をはじめ人間の家族と同じように弔うことがで...
6)高齢期(12〜14歳)
12歳は人の70歳
目の奥が白く濁って視力が衰えたり、トイレを失敗するなどが起きはじめます。
ある日、突然病気で倒れて飼い主を驚かせることも少なくない年齢で、思いがけず重病が発覚することもあります。
世界一の長寿国である日本でも70代で亡くなる方は少なくありません。
同じ犬種であっても寿命に大きな差が出てくるのが12歳を迎えるあたりからとなります。
7)超高齢期:15歳以上
15歳を超えると何かしら介護が必要になっていることも少なくありません。
犬の15歳は80代
認知機能の衰えによって夜泣きや徘徊なども起きてくる年齢です。
ここまで来たらしつけで犬の行動を改めるという考え方ではなく、別れがやってくるその日までいかに快適に過ごせる工夫を飼い主がしてあげられるか?という意識で対策を考えることが必要になります。
比較的寿命が長い小型犬であっても15歳のお誕生日を迎えることができたなら「大往生」です。
飼い主は愛犬の死を悔やむ必要はないと言えます。
18歳は100歳
15歳の壁のつぎには17歳の壁が存在します。
大切に飼われて17歳まで生きたワンちゃんはたくさんいますが、18歳のお誕生日を迎えられる子はかなり少ないです。
人でいえば100歳を超えるのに相当するものと考えられます。
20歳は110歳
犬で20歳を超えることはなかなか難しく本当にまれなケースと言えます。
このため、人間に置き換えるとギネス記録の候補者に相当すると考えられます。
教えるべき内容や教え方が年齢で変わることは意外と知られていない
実際、犬のしつけにおいてもこの年齢区分で教え方や教えるべきことが変わってきます。
とくに、子犬期と思春期~青年期(上記分類における若年成犬期)では、まったく手法が変わってきます。
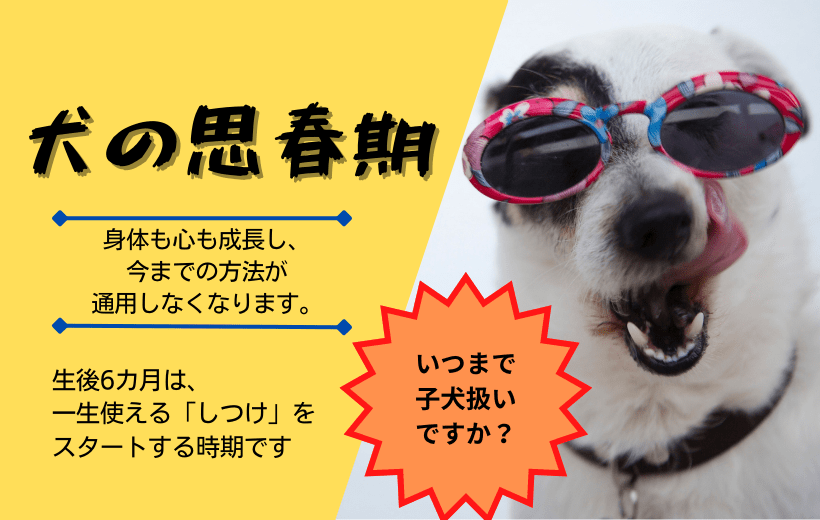
犬にも思春期があるって知っていますか? 犬は生後6カ月あたりから思春期に入ります。子犬のときとは心も体もおおきく変化していきます。飼い主はそのことを念頭において愛犬への対応の仕方を変えていく必要があります。 愛犬が我が家にやってきたばかりの頃は… 生後2カ月足らずでお家にやって...
子犬向けのしつけをいつまでもしていると、いつまでも赤ちゃんじゃないので愛犬もツラいですよ。
たとえばトイレの教え方ひとつとっても、
- 子犬期のトイレトレーニング
- 思春期のトイレトレーニング
- 老犬期のトイレトレーニング
は、まったく違うのです。

お家の中のトイレで用を足せるようにしておくことは、とても大切なしつけです。 愛犬が室内トイレで排泄ができれば…悪天候時(台風や大雪など)に、排泄のために散歩に出る必要がない 排泄のタイミングを考えて帰宅する必要がない 老犬になり身体が弱ってからも、排泄のために外に出す必要がない 排泄...
いつまでも子犬扱いせず精神年齢に応じた対応をしてあげたいですね。
関連記事

ペットショップやブリーダーから子犬を買ってきて、ワクチン接種を済ませ、ようやくお散歩デビューをしたと思ったら、あっという間に生後6カ月くらいになっています。 まだまだ可愛い赤ちゃんだと思っていたのに「思春期」と聞いて、驚く飼い主さんはたくさんいらっしゃいます。 犬にも思春期がある 犬にも思春期...
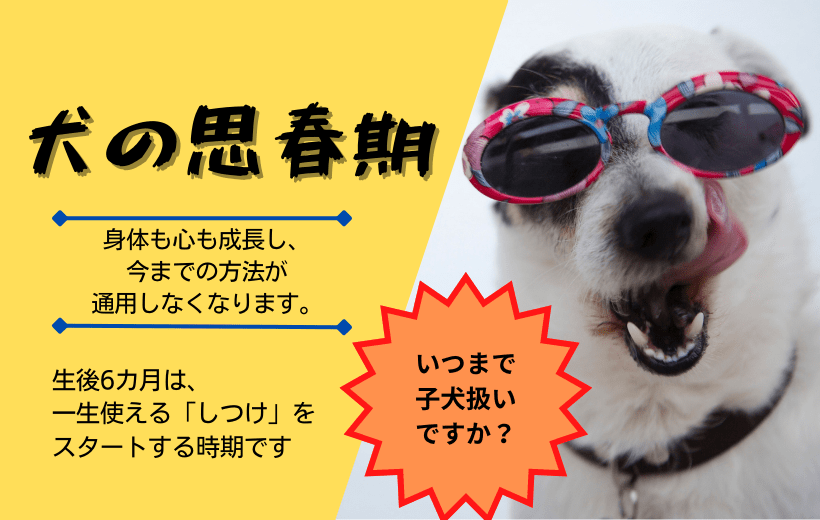
犬にも思春期があるって知っていますか? 犬は生後6カ月あたりから思春期に入ります。子犬のときとは心も体もおおきく変化していきます。飼い主はそのことを念頭において愛犬への対応の仕方を変えていく必要があります。 愛犬が我が家にやってきたばかりの頃は… 生後2カ月足らずでお家にやって...

犬と一口に言っても、選ぶときに考慮すべき項目がたくさんあります。 子犬か成犬か? 初めて犬を飼うときイメージするのはまず「子犬」でしょう。ですが、子犬を一から育てることには、多大な時間と労力を要します。まだ、心も体も未発達のため、どのように育つかは、すべて飼い主の接し方と与えた環...

犬を飼うという言葉を聞いて多くの人はペットショップで”子犬”を購入するとイメージしがちです。犬の子育ては時間との戦い しかし、初めてで何もわからない状態から子犬をちゃんと育てるのはとても大変なことです。人間の子ども同様に幼少期に心身の発達を促すことはとても重要なことです。 ...
LINEでSuzyに質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。
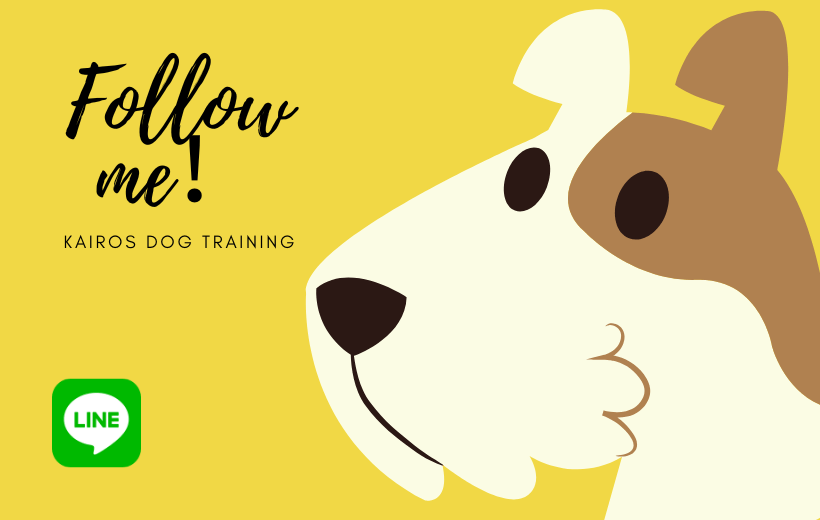
Suzyに聞きたい! 犬のしつけ情報を探してインターネットをしていてこのサイトにたどり着き、いろいろな記事を読んでみて、もっと知りたいと思うことがあったかもしれません。そんなときは、LINEお友達登録のうえ、チャットでご質問をお送りください。 質問受付中 誰かが知りたいと思っていること...