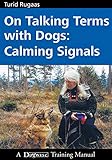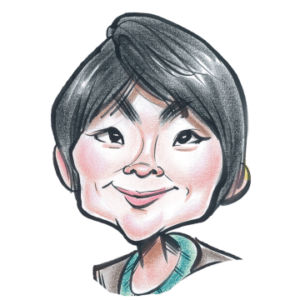静止(Freeze)
- 犬と会ったときにフリーズするのは「ゆっくり歩く」と同じ意味を持ち、相手に自分のシグナルが通じているかを判断する行為
はじめに:「フリーズ」は無言の問いかけ
犬が突然ピタッと動きを止める「フリーズ」。
まるで、「だるまさんが転んだ」をしているみたいですが、犬がする「静止」(Freeze)という行動には深い意味が隠されています。
何かに怯えているのかしら?
何かを狙っているのかしら?
と飼い主に誤解されることもあるこの「フリーズ」は、多くの場合、犬が“相手と自分の距離感”や“場の空気”を探っている状態です。
犬がする「静止」(Freeze)は、繊細なコミュニケーションである「カーミングシグナル」の一種なのです。
カーミングシグナルとは?
犬は口から発する言葉ではなく、身体を使ったサインを「言葉」として自分の感情や意図を相手に対して伝えます。
なかでも「カーミングシグナル」(calming signals)は、自分や相手の緊張を和らげるための“平和のサイン”として知られています。
ノルウェーのドッグトレーナーであるトゥーリッド・ルガース氏によって提唱されたこの概念には、27〜30種類の犬の行動が挙げられており、「静止」もその一つに含まれます。

カーミングシグナルとしての「静止」とは?
カーミングシグナルは、犬が相手との対立や緊張を回避するために使う非言語的なメッセージです。
なかでも「静止」(Freeze)は“自分から動かないことで、場を鎮める”という方法です。
これは「私は何もしないよ」という意思表示であり、相手に対して過度な刺激を与えずに相手の様子をうかがう、犬らしい思慮深さの表れでもあります。
また、これは「ゆっくり歩く」カーミングシグナルとセットで使われることも多く、相手の出方や反応を冷静に判断するための“間”として使われます。
:カーミング・シグナル(1)-350x350.png)
「静止」が使われる具体的なシーン
以下に、カーミングシグナルとして犬が「静止」することが多い場面を具体的に挙げます。
ただし、以下の状況であるからと言ってすべての「静止」がカーミングシグナルであるとは思わないことです。さまざまな条件を勘案して判断をすることが必要です
シーン1:他の犬と出会った瞬間
たとえば、お散歩中に角を曲がったとき向こうから犬が歩いてくるのに気づいた瞬間、あなたの愛犬が急にピタッと立ち止まった経験があるのではないでしょうか?
これは、相手の犬がどう出てくるかを観察するために示されるカーミングシグナルとしての「静止」であることが多いでしょう。
この間に「相手はこちらに気づいているか?」「敵意はあるか?」「自分の静止に反応してくるか?」といった情報を読み取ろうとしています。
相手との距離を測る高度な社会的行動です。
ただし、この状況は小競り合いで決着がつかずに喧嘩に発展することがあります。
このため、飼い主が母犬に代わって愛犬に「犬社会の礼儀正しい挨拶」をさせてやる必要があります。

シーン2:興奮の高まりを自分で抑えているとき
ボールを追いかけて興奮した後、犬が急に動きを止めることがあります。
これも「今、自分は落ち着く必要がある」と自制しているサイン。
犬はこうして自ら感情のコントロールを試みることもあるのです。
これは思春期以降の犬たちに見られるもので、脳の発達がまだ未熟なパピーには難しい行動でもあります。

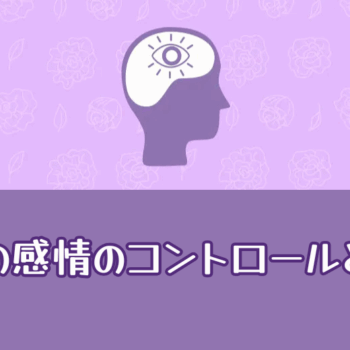
シーン3:叱られたときや緊張した場面
飼い主の語調が少し強くなっただけで、飼い主の気持ちの変化を察してフリーズする犬もいます。
動かないことで場の緊張を和らげようとするこの反応は、叱られて「萎縮」したのではなく“空気を読むための一時停止”です。
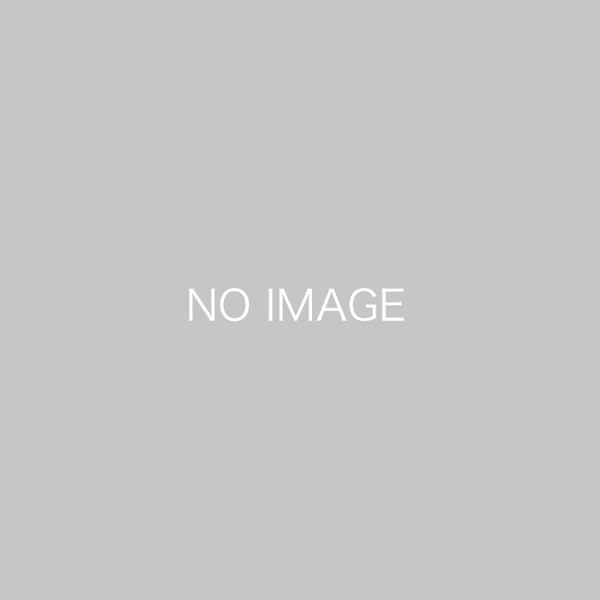
愛犬が静止したときの接し方
お散歩中に愛犬が突然立ち止まり動かなくなったとき、飼い主は「イラッ」とすることもあるでしょう。
しかし、心を乱してリードを引いて犬を引きずる前に、やらなければならないことがあります。
犬の目線を観察する
どこを見ているか、身体はどちらに向いているか、耳や尾の状態などから、何に反応して「静止」しているのかを読み取ります。
そして、この「静止」が誰かに対して発しているカーミングシグナルなのかどうかを判断します。
カーミングシグナル以外の静止なのであれば、リードで首輪に合図を送って歩き出すよう促します。
緊張を助長しない
飼い主が不安そうな表情や声を出すと、犬も「飼い主が不安に感じるなら今の状況はマズイ状況なのだな」と、緊張の度合いをどんどん高めていってしまいます。
カーミングシグナルを発している犬のそばにいるときは、人のほうも犬をリラックスさせるような働きかけをする必要があります。
飼い主と愛犬は心拍数をシンクロさせます。このため、まずは飼い主がリラックスを心掛けて愛犬の緊張を鎮めてあげましょう。
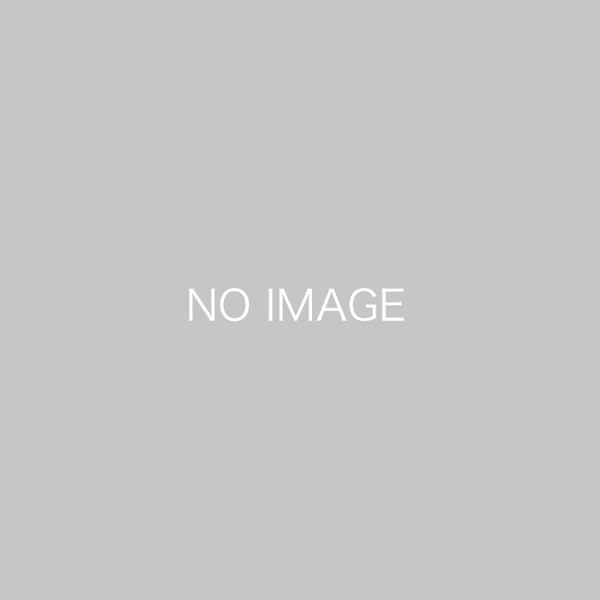
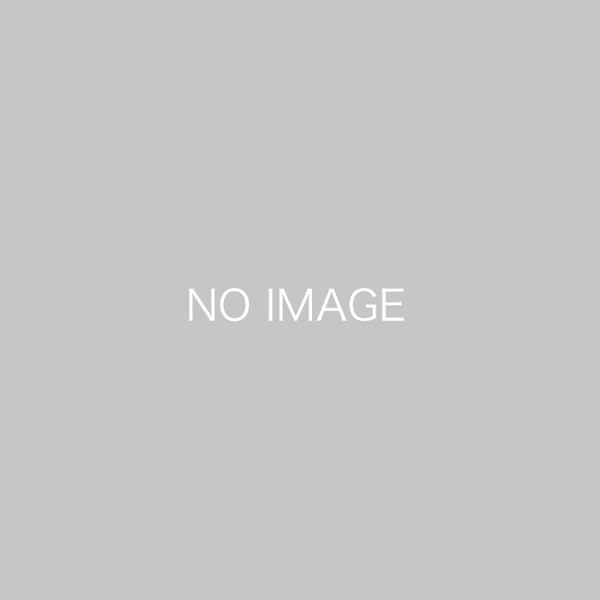
緊張感が高まってきたらどうするか
愛犬が緊張を感じる相手との距離が近づくにつれて、緊張感を高めてしまうことがあります。
狭い道路ですれ違わなければならないなど、距離をあけるのにも限界がある状況ではどうすればよいのでしょうか。
このようなときは、より効果的な別のカーミングシグナルを愛犬に追加で出させることで緊張関係を回避します。
シグナルは一つだけではなく、同時に複数を併用することで、相手に対してより詳細なメッセージを伝えることができます。
このような場面で飼い主が誘導して愛犬に使わせることができる主なカーミングシグナルには、以下のようなものが挙げられます。
追加すると効果的なカーミングシグナルの例
フリーズしている他犬への対応方法
お散歩中やドッグランなどで、ピタッと動かなくなった他犬に遭遇したら、油断せず観察することが必要です。
ただし、自分の愛犬がその犬に対して「友好的」にかかわるつもりでいるのかどうかを先に判断しなければなりません。
こちらの犬が友好的にふるまう気がないのであれば、相手の犬に近づけてはいけません。
状況の観察を優先する
「静止している=おとなしい」とは限りません。
呼吸の速さや目つき、毛並みなどを観察して、相手の犬が友好的に対応したいと考えているかどうかを探る必要があります。
相手のシグナルを尊重する
相手の犬が静止して動かない時は「これ以上近づかないで」という合図をこちらに送っているかもしれません。
無理に接触させると緊張が爆発して、攻撃されてしまうかもしれません。
噛んだ・噛まれたの喧嘩は、噛んだほうも噛まれたほうも、どちらの犬も飼い主も傷つきます。
愛犬にもカーミングシグナルを使わせる
フリーズしている相手犬にこちらの犬が突っ込んでいくとトラブルになる可能性が高いです。
もし、愛犬がフリーズしている犬にグイグイと近づいていこうとするならば、飼い主は愛犬にカーミングシグナルを出しながら近づくように誘導する必要があります。
飼い主が誘導することで使わせることができるカーミングシグナルの例
これらのカーミングシグナルは、飼い主が首輪とリードを使って誘導することで、愛犬に表現させてあげることができます。
「静止」はシグナルが通じるかを確認する間(ま)
「ゆっくり歩く」カーミングシグナルと同様、「静止」も“相手にこちらの意図が通じているのかどうかを探る”カーミングシグナルです。
とくに犬同士では、静止によってお互いに「いま、自分はどう振る舞えばいいか?」という読み合いが行われています。
このとき、相手が静止以外のたくさんのカーミングシグナルを発するようであれば、相手も友好的であると判断できます。
相手がじっとこちらを見つめてきたり、鼻先にシワを寄せていたり、背中の毛が逆立っているようであれば、距離を取るべきだということです。
静止は、まさに“その場にいながら空気を読む”ための時間なのです。
まとめ:「動かない」という深い選択
犬の「静止」(Freeze)は単なる萎縮や恐怖の現れではありません。
それは、“相手と場を読むために、あえて動かない”という賢明な選択なのです。
このシグナルを理解できると、これまで気に留めることもなかった犬たちのささいな行動が意味を持って見えてきます。
犬は言葉ではなく動きで語る動物です。
だからこそ、私たち飼い主が「止まっているその理由」に気づけるようになることが、信頼関係を築く第一歩なのです。
【一覧表】カーミングシグナル全30種
犬たちのボディランゲージのなかにカーミングシグナルに該当するしぐさは30種類あると言われます。
愛犬がよく見せる行動や、お散歩中に見かけて意味を知りたかった行動をクリックしてゼヒ読んでくださいね。
犬の「本当の気持ち」が分かるようになると愛犬との暮らしがもっと楽しくなりますよ!
- 【完全版】カーミング・シグナルをおぼえよう!
- ゆっくりと歩く(Walking slowly):カーミング・シグナル(1)
- 身体を横に反らす(Turning the side):カーミング・シグナル(2)
- カーブを描きながら近づく(Walking in a curve):カーミング・シグナル(3)
- 横を見る(See the side):カーミング・シグナル(4)
- 尻尾を振る(Wagging tail):カーミング・シグナル(5)
- 座る(Sitting down):カーミングシグナル(6)
- どこかに行ってしまう(Go away):カーミング・シグナル(7)
- 前足を上げる(Lifting ones paws):カーミングシグナル(8)
- 鼻を持ち上げる(Nose up):カーミングシグナル(9)
- 2頭のあいだを裂く(Going between, splitting up):カーミング・シグナル(10)
- あくびをする(Yawning):カーミングシグナル(11)
- 身体を振る(Shaking off):カーミングシグナル(12)
- 身体を低い位置に落とす(Lower the body):カーミングシグナル(13)
- 遊びの誘い(Going down in play position/ Play Bow):カーミングシグナル(14)
- 子犬のように振る舞う(Like a puppy):カーミングシグナル(15)
- そっぽを向く・頭を動かす(Turning the head):カーミングシグナル(16)
- 口元を後ろへ引く (Lengthen the corner):カーミング・シグナル(17)
- 歯をカチカチと鳴らす(Tang the teeth):カーミング・シグナル(18)
- 口と鼻の周りをなめる(Licking nose):カーミング・シグナル(19)
- 口をパクパクさせる(Gasp the mouth):カーミング・シグナル(20)
- 背中を向ける(Turning the back):カーミング・シグナル(21)
- おしっこをする(Peeing):カーミング・シグナル(22)
- その場所にいないように振る舞う(Acting like nothing happen):カーミング・シグナル(23)
- 静止(Freeze):カーミング・シグナル(24)
- 地面の臭いを嗅ぐ(Sniffing the ground):カーミング・シグナル(25)
- 伏せる(Lying down like the Sphinx):カーミング・シグナル(26)
- 顔の向きを変える(Turn the face around):カーミングシグナル(27)
- 目をそらす(Gaze Aversion):カーミングシグナル(28)
- 笑う(Smiling):カーミングシグナル(29)
- 転移行動(Re-directional behavior):カーミング・シグナル(30)
あなたにピッタリの情報かも?
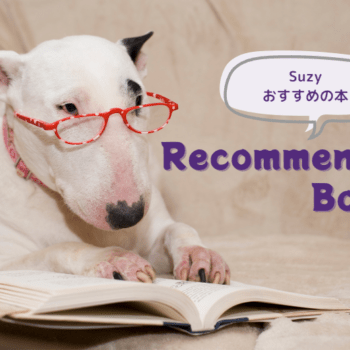

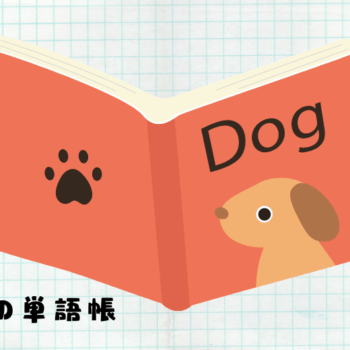

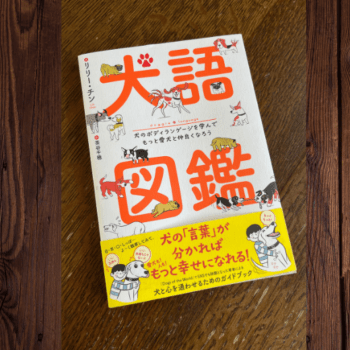
SuzyにLINEで質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。


:カーミング・シグナル(24).png)