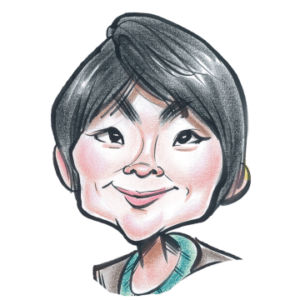飼い主と愛犬がともに幸せに暮らしていくためには、飼い主だけが頑張るのでもなく、犬だけに頑張らせるのでもなく、お互いがそれぞれにとって必要な能力を高めていくことが重要です。
その能力とはそれぞれ以下のとおり。
- 愛犬はEQ(Emotional Quotient)
- 飼い主はSQ(Social Quotient)
IQ(知能指数)は知っていたけれどEQやSQについては初めて聞いたという方もいらっしゃると思います。
本記事ではSQ、EQとはどのようなものなのか、そして飼い主と愛犬がそれぞれの能力を高めていくことがなぜ必要なのかについて解説します。
IQなら知ってるけど?
IQは英語の「Intelligence Quotient」の略で人の知能の発達を示す指数です。
知能検査の結果を平均を100として統計処理して出た数値で、高いほど知能が高いとされます。
クイズ王や学者などが入会していると話題になる「MENSA」(メンサ)の入会条件がIQ130以上であるといったエピソードなどから、IQについて知らないという人は少ないでしょう。
犬にも知能テストがある
そして、何万年も前から人とともに社会生活を営む犬たちについても「犬の知能指数テスト」があります。
「頭のいい犬は何犬?」というネタがしばしば話題になります。
こうした調査では、毎回ボーダーコリーやシェパードなどが上位にランクします。
IQ以外にもある指標
“Quotient”(指数)で人を測る指標はIQ以外にも、
- EQ(Emotional Intelligence Quotient:心の知能指数)
- SQ(Social Intelligence Quotient:社会的知能指数)
- AQ(Adversity Quotient:逆境指数)
- CQ(Curiosity Quotient:好奇心指数)
などがあります。
世間はIQだけを特別視しがちですが、これら残りの4つの指標も社会で生きていくための能力を測る重要な指標です。
なかでもEQは自己の感情を理解しコントロールする能力、SQは他者とのコミュニケーション能力や社会的な関係性を築く力のことを指します。
これらはヒトとイヌとがともに暮らしていくにあたってそれぞれが高めていくべき重要なスキルでもあります。
愛犬が高めるべきEQとは?
愛犬が高めるべきEQ(Emotional Intelligence Quotient)とは、1998年に米国の心理学者であるダニエル・ゴールマンが提唱した概念です。
感情知能や感情知性と呼ばれるものの指標で、おもに以下のようなスキルを指しています。
- 自己認識…自分の感情を理解し、なぜそのように感じているのかを把握する能力
- 自己管理…感情を適切にコントロールし、衝動的な行動や反応を抑える力
- 共感…他人の感情や視点を理解し共感する力
- 対人関係スキル…他者と良好な関係を築き、信頼と協力を促す力
- 動機付け…感情を原動力に変えて目標達成に向かう力
EQが高い人は自分自身の感情に対して適切に対応することができ、自分と他者の両方にとってより良い決断を下せる傾向があります。
EQは人間社会において仕事や家庭、友人関係における成功に重要な要素とされています。
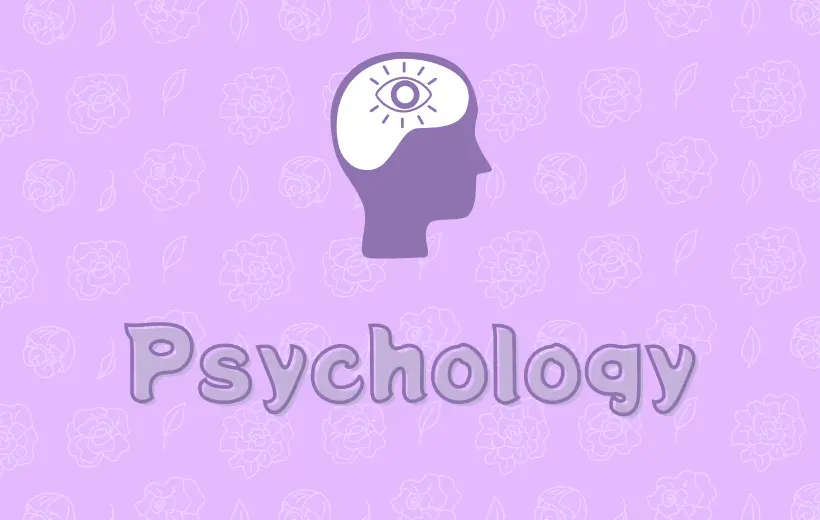
犬の「感情のコントロール」とは前頭前野の抑制機能、つまり愛犬の「我慢する心」を育てるということです。抑制機能を高めることができれば愛犬は暮らしの中で出会う物事に対して無用な不安や心配を感じることがなくなり落ち着いて生活をすることができるようになります。これは生涯にわたって心身ともに健...

フリスビーやアジリティなどのドッグスポーツやドッグダンス、そしてショーといった活動に愛犬とともに参加することは、犬とともにできる競技として注目を集めています。これらの活動は愛犬との絆を深めポテンシャルを引き出す手段として、多くの飼い主に取り入れられています。しかしながら、その一方でこ...
なぜ、家庭犬にEQが必要か?
上記の能力を犬に置き換えて考えてみましょう。
たとえば、散歩中にほかの犬に出会ったとき興奮せずに穏やかなコミュニケーションをとるためにはEQが必要です。
犬は自己の感情を上手にコントロールできるようになると、無用な争いに巻き込まれたり、不要なストレスを溜めることもなくなり生きやすくなります。
犬たちは飼い主の助けを借りながら感情を制御する術を学ぶ必要があります。
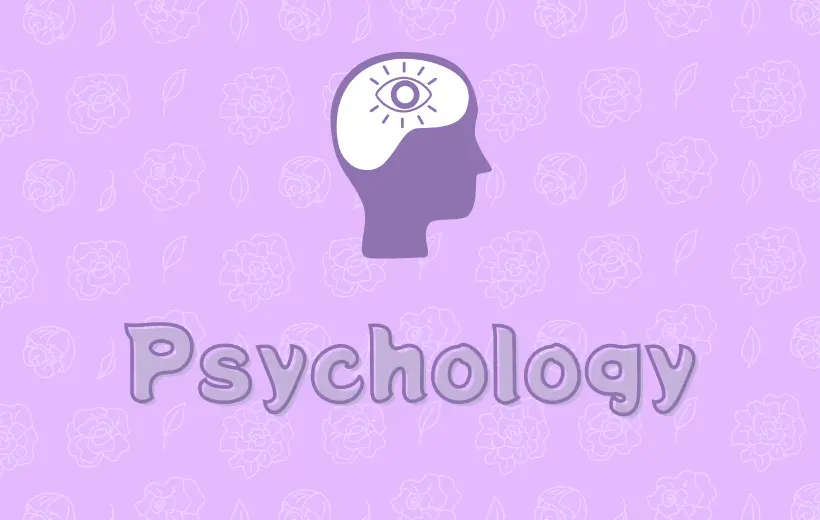
Suzyが提唱する「犬のしつけ」はエサ(フードやオヤツ)を使ってコマンドに従うことを重視していません。犬自身の自己抑制機能(自制心)を養うことと飼い主が犬のことばを正しく理解することを重要視し、これらの能力の向上に取り組むことを目的としています。「自己抑制機能を鍛える...
飼い主が高めるべきSQとは?
SQ(Social Intelligence Quotient)はEQを提唱したダニエル・ゴールマンが2007年に提唱した概念です。
社会的な状況での知性や他者との円滑な関係を築く力を指します。
具体的には以下の能力を測るものです。
- 状況理解…社会的な状況や集団の雰囲気を読み取る力。場の空気を感じ取ったり、他者の意図を察知したりする能力
- コミュニケーションスキル…効果的な会話や非言語的なコミュニケーションを通じて、他者と理解し合う力
- 聞く力と話す力…言葉遣いや表情、ボディランゲージなどを使って思いを伝える力
- 関係管理…他者と良好な関係を築き維持する能力。他者に共感し協力し合える関係をつくる力
- 影響力…他者に良い影響を与えたりグループでの信頼と調和を生む力
- 適応力…さまざまな人びとや文化、状況に柔軟に対応する能力
SQが高い人は社会的な場での判断力や適応力が優れておりチームワークやリーダーシップ、対人関係において有利に働くことが多いとされます。
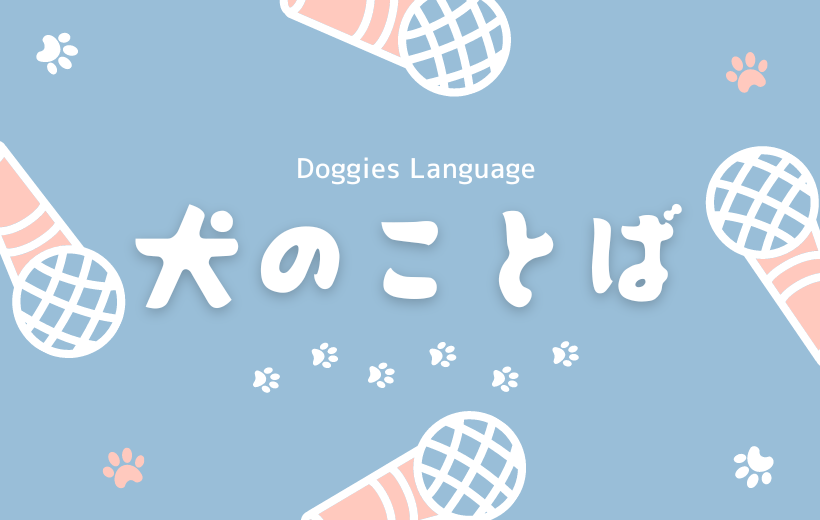
犬たちには「犬のことば」があるということはすでにご存じかと思いますが、ここで改めて犬たちのことば「犬語」についてまとめてみたいと思います。 犬の言葉は世界共通! 私たち人間の世界では国によって使う言語が異なり、ほかの国へ行くと翻訳ツールがなければさっぱり言葉が通じません。それどころかこん...
なぜ飼い主にSQが必要か?
まず、飼い主にが愛犬との関わりにおいてSQが影響する点について考えてみましょう。
飼い主は愛犬がほかの犬や人たちとうまく関係を築くための調整役を務める必要があります。
飼い主は調整役
飼い主がSQの力を高めていくことができれば、愛犬が他者(犬に対しても人に対しても)と安全に楽しく交流できるようになるのです。
SQ力の高い飼い主は、愛犬がほかの犬や人と接触する際に、相手の様子(犬であれば友好的なのか敵対的なのか、人であれば犬と接するための知識を備えているのか)を見極めることができます。
そのうえで、安全に関われる距離感やレベルを調整するなどして、愛犬に無用なストレスを与えることなくスムーズな社会交流をさせてあげることができます。

以前、犬のしつけをするにあたって大切な「3原則」についてご紹介しました。こうした、生活に即した目的を叶えるための「しつけ」の取り組みの過程で、愛犬に「あるもの」が育っていきます。 心の器 それは「心の器」です。心の器とは、物事に対する許容範囲やキャパシティーのことを指しま...
愛犬の能力を引き出す
また、SQ力の高い飼い主は愛犬のEQ力を引き出すサポートをすることもできます。
たとえば、SQ力の高い飼い主は犬が過剰に興奮してしまう状況において、リードワークや言葉かけを通じて愛犬に感情のコントロールを促してやることができます。
飼い主が愛犬を適切に落ち着かせる行動がとれるようになると、困難だと思われていた状況を乗り越えることができます。
そして、愛犬は飼い主の助けを借りて「無理!」と思っていた状況を冷静に乗り越える経験を積むことができます。
こうして、愛犬のEQは鍛えられていくのです。
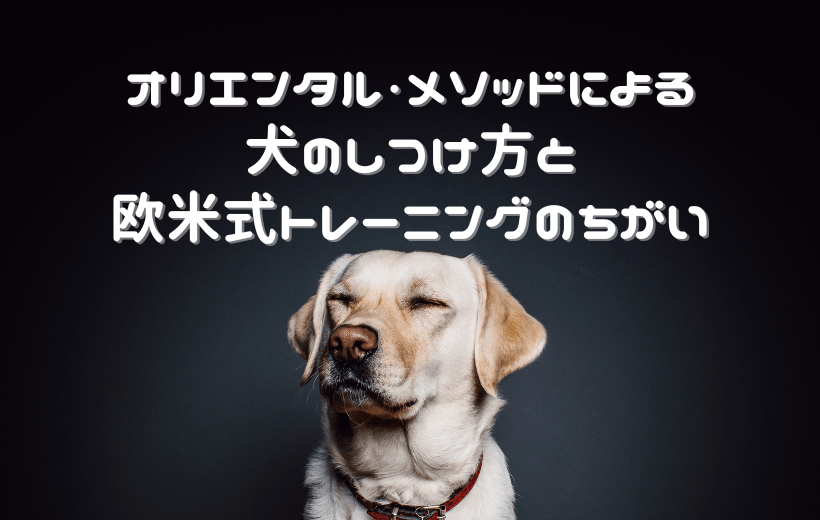
犬のしつけは愛犬との生活をより楽しく充実したものにするために欠かせないものです。しかし、多くの飼い主さんたちが「何を」「どのような方法で」教えれば良いのかということに悩んでいるのではないでしょうか。日本では2000年頃からご褒美にフードを与えて行う「欧米式ドッグトレーニング」が主流に...
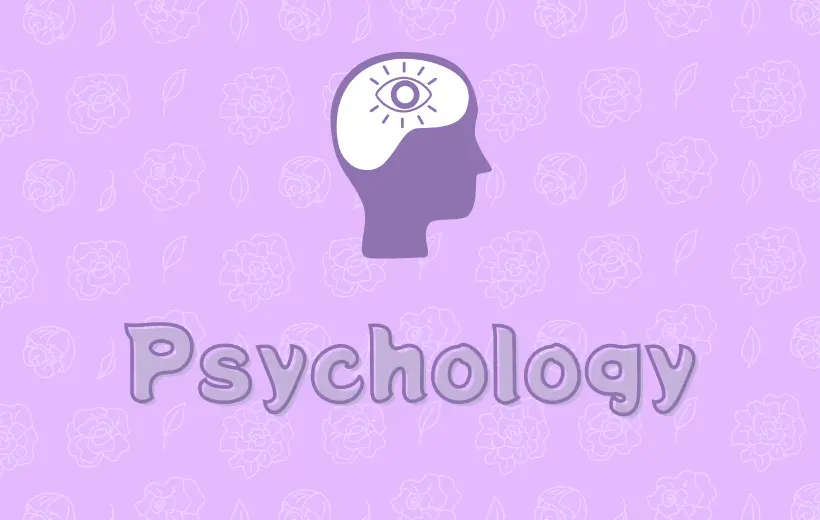
仲間や同僚などがお互いの行動や生産性に影響を与え合うことを指す「ピア効果」という専門用語があります。「朱に交われば赤くなる」ということわざは、まさに「ピア効果」のことを示すものです。 ピア効果とは ピア(peer)は、年齢・地位・能力などが同等の者、同僚、同輩、仲間を意味する英語で、教育...
まとめ
愛犬が「感情のコントロール力」すなわちEQを育むには、飼い主には愛犬を導くためのSQの力が必要不可欠です。
飼い主であるあなた自身がSQを高めることこそが「犬のしつけ」であると言えるのです。
飼い主が高いレベルのSQを発揮することで愛犬との信頼関係が深まり、愛犬との豊かな関係を築くことができるのです。
関連記事
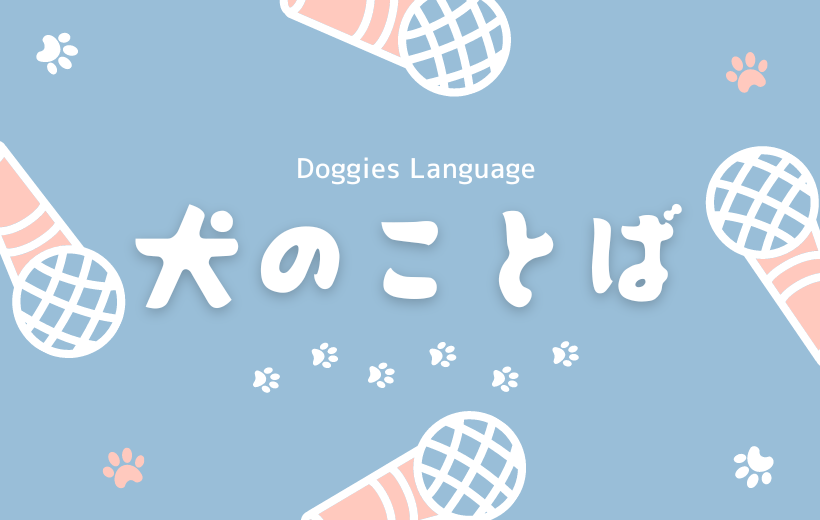
犬たちには「犬のことば」があるということはすでにご存じかと思いますが、ここで改めて犬たちのことば「犬語」についてまとめてみたいと思います。 犬の言葉は世界共通! 私たち人間の世界では国によって使う言語が異なり、ほかの国へ行くと翻訳ツールがなければさっぱり言葉が通じません。それどころかこん...
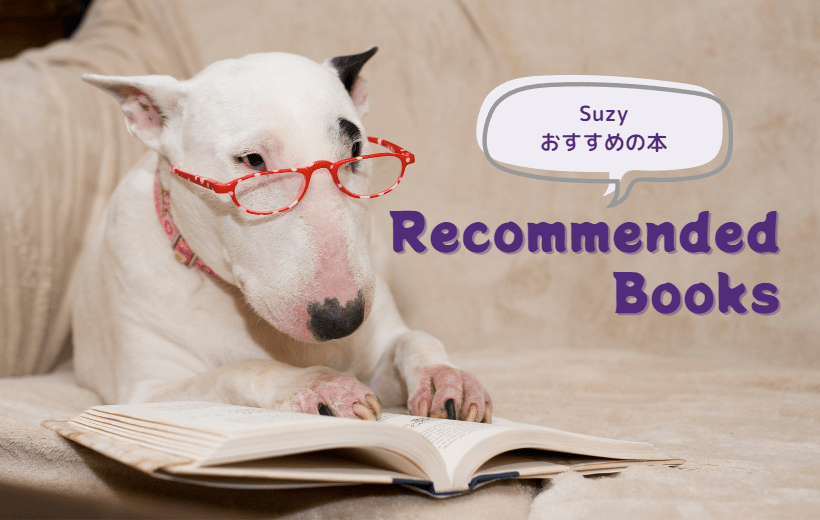
犬との暮らしについてもっと知識を得たいとき、もっと知りたいことがあるとき、本を読むことも大切です。 ドッグトレーナーが必読を勧める2冊 Suzyが絶対に読んでほしい本は以下の2冊です。発行年は古いものもありますが、内容はまったく古くありません。「犬のしつけ」の名著です。 1冊目...
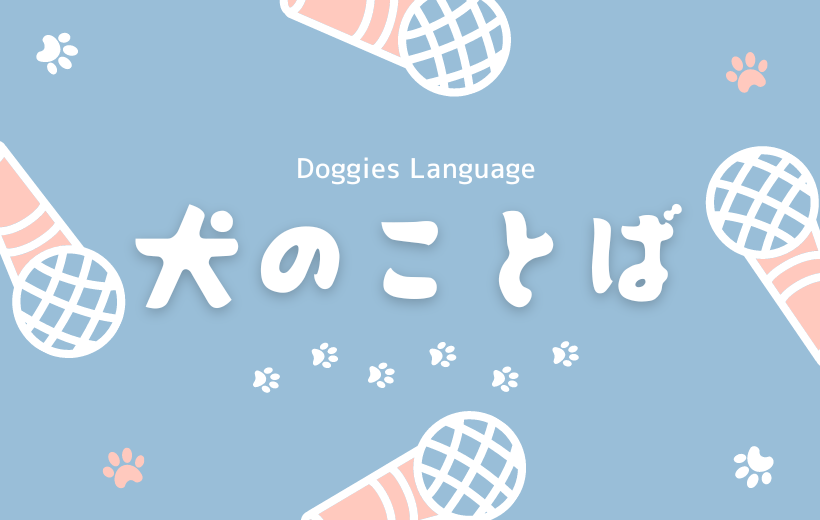
犬たちは日本語を話しませんが、犬のことばをもっています。犬とともに暮らす人は、犬のことばを学びましょう。犬の気もちを読み取るスキルを身に付けさえすれば、心のボタンを掛け違えることはなくなります。そして、飼い主か愛犬のどちらか一方だけがガマンを強いられることのない、イヌ・ヒトの...

「叱ってはいけない」という方法のしつけがブームになって久しく、そのように教えるドッグトレーナーも多いです。 Suzyのところへやってくる飼い主さんのなかにも「犬を叱ったら嫌われてしまうのでやりたくありません」と、真顔で言ってくる飼い主さんもいらっしゃいます… 「褒めるしつけ」を勘違いしていません...

どんな犬のしつけマニュアルにも「褒めましょう」と書いてあり、犬のしつけにおいて「褒めること」は非常に重要です。しかし、ただやみくもに褒めればいいというものではありません。 2種類ある「犬のほめ方」 犬の褒め方には、正反対の効果をもつ2種類があるのをご存じでしょうか?心を落ち着...
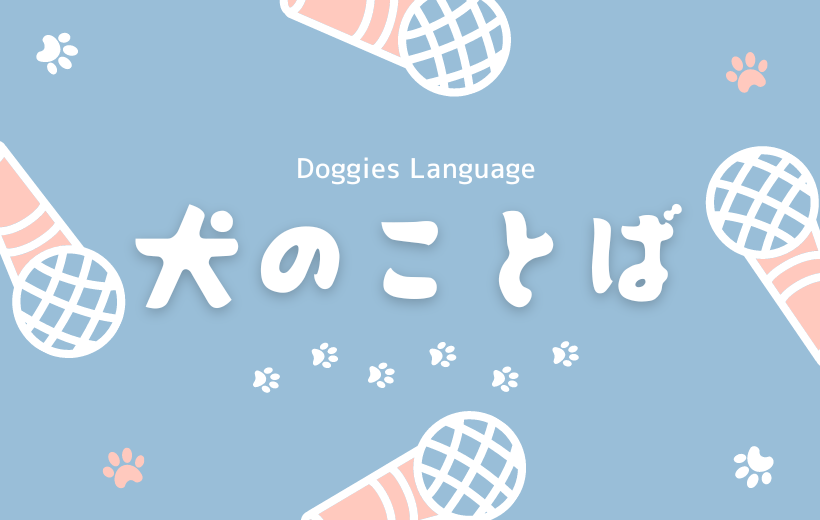
「犬をしつける」というとき、ヒトはなぜだか「命令口調」になります。これまで、テレビなどで見たりする警察犬などの「訓練」のイメージで、そのような口調になってしまうのかな?と考えていましたが、夕方のお散歩で出くわす小学生の子どもたちが、我が家の犬を見つけて「お手!」とか「オスワリ!」とか...
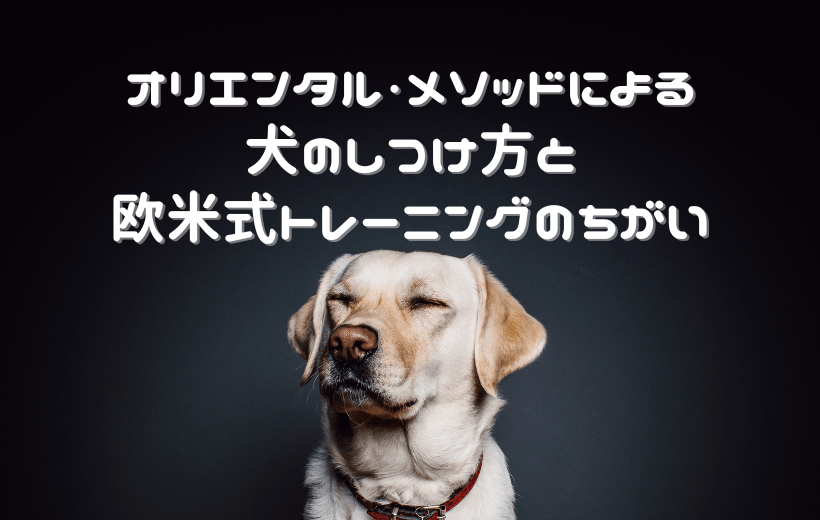
犬のしつけは愛犬との生活をより楽しく充実したものにするために欠かせないものです。しかし、多くの飼い主さんたちが「何を」「どのような方法で」教えれば良いのかということに悩んでいるのではないでしょうか。日本では2000年頃からご褒美にフードを与えて行う「欧米式ドッグトレーニング」が主流に...
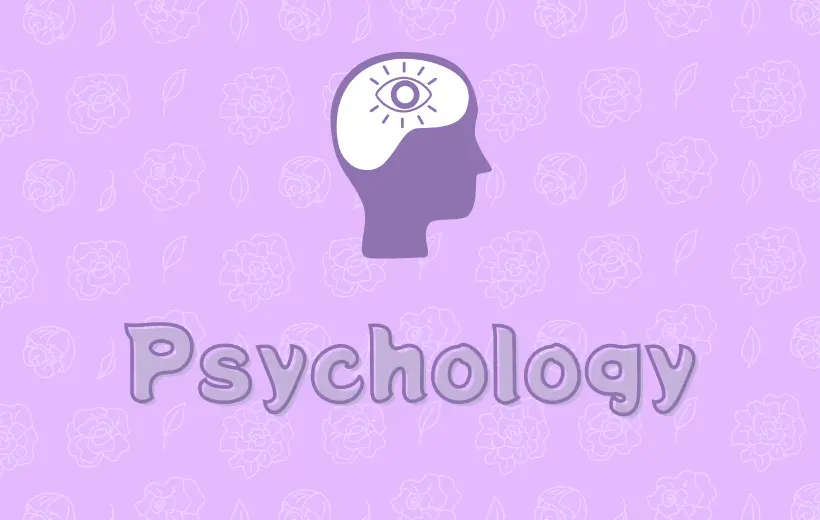
仲間や同僚などがお互いの行動や生産性に影響を与え合うことを指す「ピア効果」という専門用語があります。「朱に交われば赤くなる」ということわざは、まさに「ピア効果」のことを示すものです。 ピア効果とは ピア(peer)は、年齢・地位・能力などが同等の者、同僚、同輩、仲間を意味する英語で、教育...

ご近所との関係をよくする 「犬のしつけ3原則」で、取り上げた3つの項目の最後は、「ご近所との関係をよくする」でした。 過剰に強い同調圧力の文化をもつ国、ニッポン 日本社会の欠点として、過剰に同調圧力の強い文化が問題視されています。そんな環境において、「他人の目を気にしない」とい...
LINEでSuzyに質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。
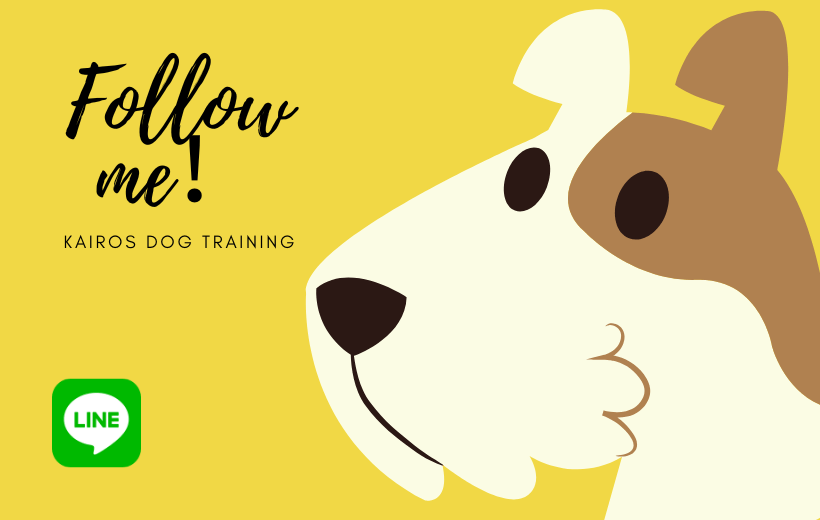
Suzyに聞きたい! 犬のしつけ情報を探してインターネットをしていてこのサイトにたどり着き、いろいろな記事を読んでみて、もっと知りたいと思うことがあったかもしれません。そんなときは、LINEお友達登録のうえ、チャットでご質問をお送りください。 質問受付中 誰かが知りたいと思っていること...