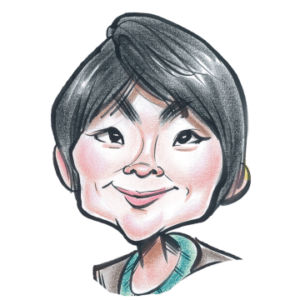犬を飼う楽しみの一つは、お散歩でいろいろなワンちゃんと出会い、交流をもつことではないでしょうか?
お散歩中に出会うほかの犬に対して、吠えたり噛みついたりする、または他の犬に異常に怯えるなど、お散歩の悩みを抱える飼い主さんはとても多いです。
じつは、家庭で暮らす犬たちのほとんどは、母犬から犬社会の社交スキルを学ぶ前に親元を離れて人間と暮らし始めたため、犬社会の礼儀やマナーを身につけていません。
ほかの犬との正しい関わり方知らないために、適切な行動をとることができない犬がとても多いのです。
ほかのワンちゃんともっと仲良くしたい、
毎日のお散歩をもっと楽しくしたい
と思ったら、
お散歩中の行動のすべてを、犬任せにしていては何も解決しません。
母犬から犬社会を教わる機会がなかったのであれば、飼い主が母犬に代わって愛犬に犬社会のルールを教えてあげなければなりません。
この記事では、あなたの愛犬が日常生活において、ほかの犬と上手く関わっていける「コミュ力のある犬」になるために、飼い主として犬社会のマナーをどのように教えればよいのか、その方法を具体的に解説します。
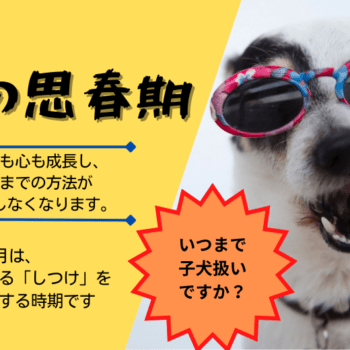
よその犬とのかかわり方
お散歩中に、よその飼い主さんが連れているワンちゃんと遭遇したら、どのように振舞えばよいのか分からず、戸惑っている飼い主さんは少なくありません。
犬任せはNG!
だからといって、その状況をすべて愛犬任せにしてはいけません。
飼い主のいない犬同士は、犬任せで決着をつけるのが当たり前ですが、家庭犬においては、「飼い主」の存在が大きく影響します。
家庭で暮らす犬同士の交流を100パーセント犬任せにすることは、決して良い結果になりません。
強い者が「絶対」の犬社会
もし、あなたの愛犬があなたの飼い犬でなく、相手のワンちゃんにも飼い主がおらず、お互いがただ「犬」として振舞えばよいのであれば、「強い者が絶対」という犬の本能に則って行動すればよいでしょう。
このルールの下、弱いほうの犬は、食べ物を奪われても大怪我をさせられても、それを当然のこととして受け入れます。
ひとたび自分の負けを認めれば、自分より強い者に対して、何をされても決して文句を言いません。
強い者の怒りに触れて弱い者が殺されたとしても、それが当たり前なのが「犬」の世界です。
ただし、簡単に相手の命を奪うことができる社会である反面、争いに発展しないためのコミュニケーション術(カーミングシグナル)もきちんと備えているのが犬社会です。

飼い主に紐づく「家庭犬」
しかし、野犬でなく人に飼われている「家庭犬」の背後には、必ず人間の「飼い主」が存在します。
一方的によその犬に襲われ、愛犬がケガをさせられて、何も感じない飼い主はいません。
ケガをしなくたって、うちの子が心に傷を負わされた!と根に持つのが飼い主というものです。
家庭犬同士の交流においては、つねに相手の「飼い主」も意識したかかわり方をしなければなりません。
「安易な犬任せ」は、トラブルしか生まない
また、犬は生まれつき「人間社会のルール」も知りません。
飼い主から人間社会のルールを教わることができなければ、犬社会のルールに基づいた価値観で行動します。
つまり、「強い者が絶対」という行動をとります。
このため、ほかの犬との交流を犬任せにすることはトラブルの元となるのです。

犬と人のルールを掛け合わせた特殊な社交術
われわれ飼い主は、犬社会のルールと人間社会の常識をうまく掛け合わせた方法で、ほかの犬とのかかわり方を愛犬に教えていかなければならないのです。
しかし、犬が人間社会のルールを本能的に知らないのと同じように、われわれ飼い主も犬社会のルールを生まれつき知っているわけではありません。
まずは、犬同士の挨拶のルールを知ることからスタートです。
犬社会の挨拶ルール
犬の社会は人間とは全くちがう方法で挨拶をします。
とくに、すべての飼い主さんに知ってほしいのが、相手の目をじっと見つめさせるのは危険であるということです。
目と目があったら喧嘩の合図
人間同士は出会ったら相手の目をしっかりと見て挨拶をするのが礼儀です。
しかし、犬たちの世界では「真逆の解釈」が行われます。
しかし、初対面や、さして親しくない相手と接する場面で、相手の目を凝視するのは、相手に対して喧嘩を売っている行為なのです。
「ご挨拶するのよ~」と言って抱き上げて、わざわざ相手の犬の目を、じっと見させてしまう飼い主さんはとても多いです。
良かれと思って、真逆のことを愛犬に教えてしまっているのです。
-350x350.png)
:カーミングシグナル(16)-350x350.png)
正式な挨拶:お尻の匂いを嗅ぎあう
犬同士の正式な挨拶は「お尻の匂いを嗅ぎあう」ことです。
人間社会ではありえない挨拶方法のため、驚く方も少なくありません。
相手のお尻に鼻先を持っていくことを「恥ずかしいこと」と、勘違いしている飼い主さんもいます。
個人情報の宝庫「肛門腺」
犬は肛門の周囲にある肛門嚢(こうもんのう)に、「肛門腺」という強い獣臭をもつ液体を溜めています(トリミングサロンや動物病院で絞ってもらうアレです)。
この肛門腺には、犬の個人情報のすべてが詰まっています。
犬たちは相手のお尻に近づいて肛門腺の匂いを嗅ぎ、相手の犬の性別や性格、年齢、健康状態などを知り、その相手とどのように付き合うべきかを判断します。
これが「犬同士の挨拶」なのです。

カジュアルな挨拶はトラブルのもと
また、犬たちは肛門腺のほかにも、耳の穴や口の中からも独自の匂いを発しています。
この匂いから相手の情報を探ろうとして、最初から相手の顔回りの匂いを嗅ごうとする犬もいます。
しかし、犬によっては、最初から顔のほうに近づいてくる相手の犬を警戒して、喧嘩に発展することが少なくありません。
嗅ぎ逃げタイプがやりがち
「嗅ぎ逃げ」とは、自分は相手のお尻の匂いを(相手が嫌がっていても)しつこく嗅ぎに行くくせに、自分のお尻の匂いは頑として嗅がせない犬の行為のことを指して言います。
犬のお尻の匂いにはその犬の個人情報のすべてが詰まっています。
相手のすべての情報を暴いておきながら、自分の情報は一切開示しないというのは、犬社会において非常に失礼なマナー違反の行為であり、犬同士のトラブルの大きな原因となっています。
相手の顔に自分の顔を近付けていれば、相手の顔が自分のお尻に近づくことができないため、自分のお尻の匂いを嗅がれたくない犬が、顔から挨拶をしに行く傾向があるように思います。
自分が気にしない性格だから…
もしくは、小さなことは気にしないおおらかな性格の犬や、テンションが高くせっかちな犬が最初から顔同士の挨拶をしようとする傾向があります。
飼い主の無知に起因するケースも
よその犬同士が顔を突き合わせて挨拶しているのを見た飼い主が、自身の愛犬をほかの犬と挨拶させたいと思って愛犬を抱き上げ、愛犬の顔を相手の犬に近づけて挨拶させようとする場面によく遭遇します。
しかし、子犬が自分より年上の犬に対して顔から挨拶をする(しかも上から覆いかぶさるようにして)のは本来とても無礼な行為となります。
ただ、子犬のうちは無礼な行為を大人に許されることが多いため、幸いにもトラブルにならずに済んでいるだけなのです。
抱っこされ逃げ場のない状態で無理やり無礼を働かされているうちに、あなたの愛犬はほかの犬が怖くなったり嫌いになってしまいます。
もし、あなたがこのような方法で愛犬をほかの犬と交流させているのであれば、今すぐやめなければいけません。
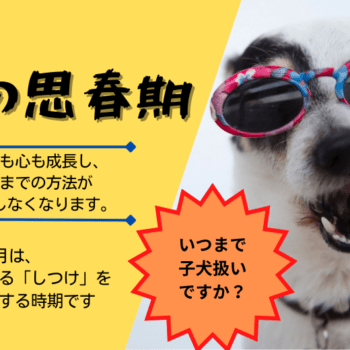
合わない相手は避ければいいのか?
少なからぬ飼い主さんたちがプロであるトレーナーや動物病院から「向こうから犬がやってきたら反対方向に向かって歩き、ほかの犬と近づくことを避けましょう」と教わっています。
しかし、いつまでもほかの犬を避けて散歩をしていたら、何時間経っても家に帰ることができません。
また、緊張を強いられ、逃げるようにお散歩をしなければいけない生活が続くことを、「辛い」と感じる飼い主さんも少なくありません。
飼い主が「辛い」と感じれば、その犬は(まさか自分が原因とは思わず)もっと神経質になり、状況は悪化していきます。
「避ける」という方法は解決法ではありません。
その状況を克服するプロセスにおける、ごく初期の一次的な「回避手段」でしかありません。
避けるほど、苦手なことが増えていく
苦手をいつまでも避けていては、生活を前向きに変えることができません。
それどころか、苦手なことの許容範囲がどんどん狭くなっていき、今まで「大丈夫」だったことも「ダメ」になっていきます。
そして、状況はどんどん悪化していくのです。
生活するうえで「必要な苦手」は「向き合って乗り越える」ことでしか解決できません。
乗り越える方法=感情のコントロール力UP!
愛犬に過敏すぎる感情をコントロールする術を身につけさせ、過剰に広すぎるパーソナルスペースを適正な広さまで縮めてあげることが本当に犬を救う手段です。
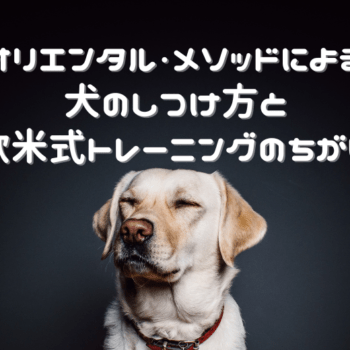
卒のない「大人の挨拶」を身につけよう
もちろん、世の中のすべての犬と親友になる必要はありません。
わたしたち人間だって、好きな人や苦手な人はいます。
全人類に対して平等に愛着を感じているということはあり得ません。
ただし、われわれ人間は大人になれば、苦手な相手に対して「お前は嫌いだからあっちに行け」と叫びながらすれ違うような行動はしないはずです。
また、いくら嫌いな相手がいても、すれ違いざまに刃物でいきなり刺したら、刺した人は完全な犯罪者です。
私たち人間は大人になれば、たとえ近所や同僚に苦手な人物がいたとしても、必要以上に深入りせず、当たり障りのない挨拶を交わす間柄をキープして、波風を立てることなく上手く生活(もしくは、しようと努力)しているはずです。
わざわざ目の前に行って怒鳴り散らしたり、相手を傷つけたりしないはずです。
飼い主家族とともに暮らす家庭犬に必要な社交もこれとまったく同じです。
犬が身につけるべき「大人の挨拶」
もし、相手の犬のことを「なんだか苦手だな」と感じても、過剰に怯えたり、吠えたり、攻撃したりせず「私は今、あなたと深く交流したいとまでは思っていません」という意思を、過不足なく相手に失礼なく伝えることができれば、それで十分なのです。
苦手な犬がいたとしても、これを避けて生き続けるのではなく、大人の犬としての振る舞いを身につけさせてあげればよいのです。

あいさつの順序
では、飼い主はそうした挨拶の方法を、愛犬にどうやって教えればよいのでしょうか。
- 飼い主同士が挨拶
- 愛犬を保定
- 匂いを嗅いでもらう
- 匂いを嗅がせてもらう
- 相性の観察
1)まずは飼い主同士が声を掛け合う
冒頭でお話したように犬同士の挨拶を完全に犬任せにしてはいけません。
まずは、相手の飼い主さんと目があったらお互いに視線を合わせ、にこやかに明るい声で挨拶をします。
なぜ、にこやかでなければいけないかというと、犬は飼い主の感情を読み取る天才であり、飼い主が緊張したり不安を感じていれば愛犬が相手の人や犬を警戒してしまうからです。
また、声が暗ければ相手の飼い主さんも愛犬も警戒させてしまいます。
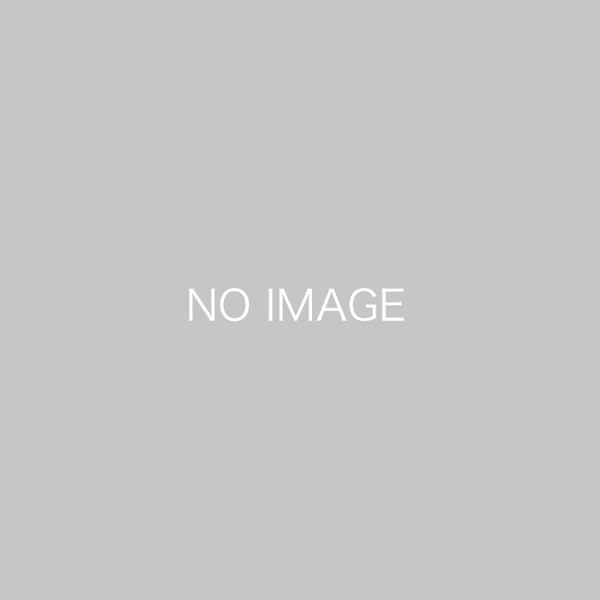
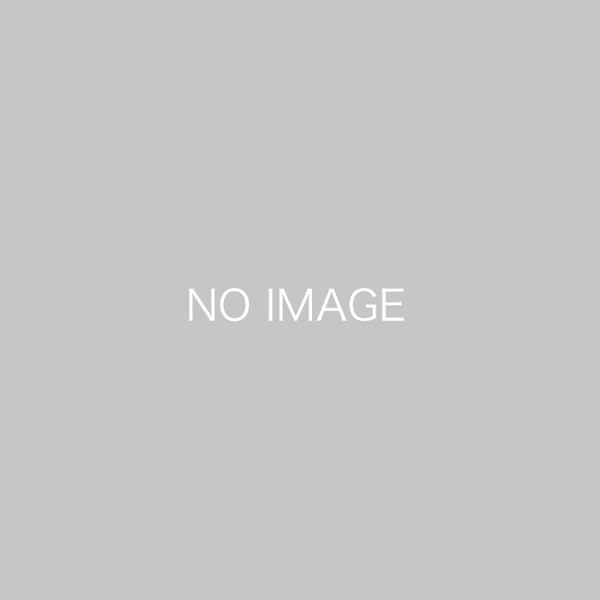
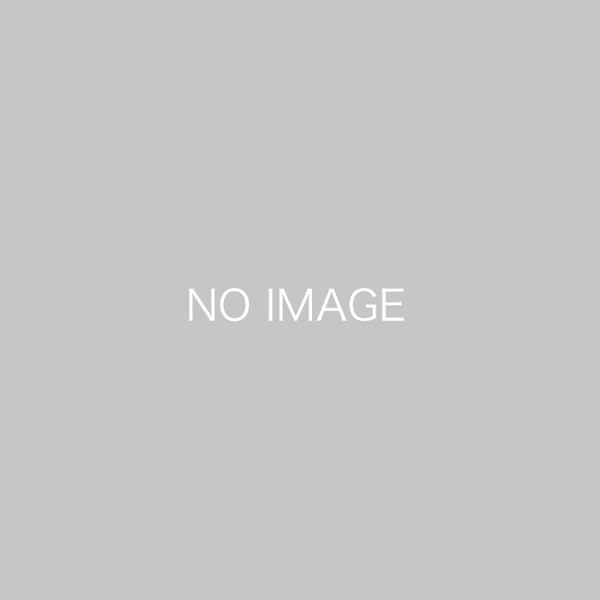
愛犬は自分より後ろに
このとき自分の愛犬は、自分の身体よりも前に出ないように横または後ろに控えさせます。
なぜなら飼い主よりも前に出ることを許してしまうと、愛犬は飼い主を守らなければいけないと勘違いして相手を過剰に警戒してしまうからです。
吠えたらすぐに止める
もし、このとき相手のワンちゃんに対して愛犬が吠えるようであれば、すぐに叱って必ず止めます。
もし、吠えている犬をそのままにしていれば、自分の吠え声にさらに興奮してしまい、挨拶どころではなくなってしまいます。

相手の飼い主さんに尋ねること3つ
上記の点に気を付けたうえで、相手の飼い主さんに以下の3点を訪ねてみましょう。
- あなたの愛犬と挨拶をさせてもらえるか?
- 相手の犬の年齢
- 相手の犬の性別
このほか、犬種や名前を聞くと、飼い主同士の会話がはずみます。
もし、あれこれ尋ねる余裕がなかったとしても、「あなたの愛犬と挨拶をさせてもらえるか」だけは必ず聞きましょう。
まちがっても、飼い主に断りなく相手の犬に自分の犬を近づけてはいけません。
2)保定をする
本来、犬同士の正式な挨拶のルール上、年長の犬から先にお尻の匂いを嗅ぐ権利があります。
しかし、相手の飼い主さんはそのルールを知らないかもしれません(ほとんどの飼い主さんが知らないです)。
このため、年齢や性別の条件に関わらず、声をかけたほうの飼い主の犬から、お尻の匂いを先に嗅いでもらいます。
安全にお尻の匂いを嗅いでもらうコツ
犬同士で挨拶をする際に、率先して自分からお尻を差し出せるワンちゃんはなかなかいません。
このため、相手のワンちゃんがお尻の匂いを嗅ぎやすいように、飼い主が愛犬をしっかりと保定します。
保定のやり方は、以下のページで詳しく紹介しています。

3)匂いを嗅いでもらう
しっかりと保定をしたら、相手のワンちゃんに愛犬のお尻を向けて、匂いを嗅いでもらいます。
もし、このとき相手のワンちゃんが、顔に向かって挨拶に来ようとしたら「今日はお尻のご挨拶でお願いしまーす」と明るく言って、愛犬のお尻を相手の犬の鼻先にもっていきます。
そして、愛犬のお尻の匂いを嗅いでもらいましょう。
後ろを振り向かせない
このとき、お尻の匂いを嗅がれている愛犬は、後ろの犬の反応が気になって、後ろを向こうとすることが多いです。
しかし、ここで後ろを振り向いて、匂いを嗅いでいる犬と目が合ってしまうと喧嘩に発展してしまいかねません。
このため、愛犬の頬っぺたと目を手のひらで覆い隠すようにして、自分の肩にしっかりと引き付け、愛犬が後ろを振り向いて後ろの犬と目が合うことがないようにすることが重要です。
我慢していることをよく褒める
飼い主は愛犬が匂いを嗅がれているあいだ、つい愛犬の匂いを嗅いでいる相手の犬の様子をじっくりと観察してしまいがちです。
しかし、このとき飼い主は匂いを嗅がれている愛犬の様子を観察し「我慢してじっと待っている」ことを優しい声で褒めてあげます。
吠えたら「すぐ」にやめさせる
もし、吠えてしまったら1秒でも早く止めます。
そうしないと、吠え声で双方の犬が興奮してしまいます。
「止める」のであって声を出して「叱る」必要はありません。
吠えを止めるには愛犬の頬を押さえている手を下あごに移し、マズルを下から上に軽く持ち上げるように固定して、物理的に口が開かないようにします。
犬の身体は吠えるとき、下あごを動かして口を開き、声を出す仕組みになっています。
このため、下あごの位置を固定されると口を開くことができなくなるのです。
このとき、マズルを押さえている手の親指と人差し指をUの字にして、少し力をかけてマズルを挟むようにするのがコツです。
また、このときに飼い主が吠えに反応して、緊張したりイライラしたりしないように気を付け、心をニュートラルに保つようにすることも忘れないでください。
保定を解除する
匂い嗅ぎが終わって相手のワンちゃんが離れたら、「ヨシ、いいよ」と声をかけ保定している両手を離して愛犬を解放します。
解放したとき愛犬はまるでシャンプー後のように、ブルブルと全身を震わせるかもしれません。
このブルブルは我慢していた気持ちを発散させるカーミングシグナルです。
我慢できたことをしっかりと褒めてあげましょう。
このとき、興奮させるようなほめ方をしてはいけません。
愛犬がリラックスして穏やかな気持ちになるように、落ち着かせる褒め方をするのがコツです。
赤ちゃんを寝かしつけるような、静かで穏やかなトーンで話しかけます。
まちがっても、愛犬の身体をボンボン叩いたり毛をわしゃわしゃと掻いたりして、興奮させるような褒め方をしないように気をつけてください。
器の大きな一目置かれる存在に
こうした成功体験の積み重ねが、愛犬の心に「自信」(自己効力感)を育みます。
その結果、ほかの犬と接する際に、堂々とした振る舞いができるようになっていきます。
いつでも堂々として落ち着いている犬は、「器の大きな犬」としてほかの犬から尊敬され一目置かれる存在になります。
犬も飼い主も心の底から、お散歩を楽しめるようになります。

4) 匂いを嗅がせてもらう
今度は入れ替わりに、相手のワンちゃんにこちらが匂いを嗅がせてもらう番です。
匂い嗅ぎは相手の飼い主次第
お散歩中に出会ったワンちゃんの飼い主さんが、犬同士の正しい挨拶の方法を知っている確率はとても低いです。
このため、もしかしたら自分の愛犬が匂いを嗅いだだけで、立ち去ってしまうかもしれません。
そのばあいは仕方がありませんので「嗅がれる経験」を積めたことでヨシとして終わりにします。
このときも、飼い主が「嗅がせてもらえなくて残念だった」と思ってしまうと、愛犬はそれに反応していら立ち、相手の犬に向かって吠えるなど攻撃的な態度を示してしまいかねません。
「嗅がれるあいだじっと我慢出来て偉かったね」と、愛犬のことをしっかりと褒めることを忘れないでください。
嗅がれる経験のほうが重要
Suzyの経験上、ほかの犬とのかかわり方を知らなかった犬たちのほとんどが、50~60頭くらいの犬に匂いを嗅いでもらう経験を積むことで、ほかの犬と対面する際の緊張や不安を感じなくなり、上手にほかの犬とかかわることができるようになっていきます。
できるだけ短期間に、1頭でも多くの犬にお尻の匂いを嗅いでもらうことが大事なのです。
このため、相手のワンちゃんにお尻の匂いを嗅がせてもらえなかったとしても、決してそのことでガッカリする必要はありません。
むしろ、お尻の匂いを嗅がれることを、お散歩中のゲームにして愛犬と楽しんでしまえば良いのです。
5) 相性を観察しよう
お互いにお尻の匂いを嗅ぎあったあとは、(あきらかに敵対心を見せていない犬同士のばあいは)犬同士に挨拶を任せて少し様子を観察します。
気が合いそうなら
気が合う同士だったら、以下のような反応が見られるでしょう。
- クルクルと回りながら改めてお互いのお尻の匂いを嗅ぎあう
- お互いに顔を突き合わせて挨拶を始める(ただし、このときに双方の表情に緊張は感じられない)
- 遊びに誘う&誘いに乗る
そのまま、一緒に遊んだりお散歩できたりしたら楽しそうです。
フツーのばあい
じつは、「気が合うというほどの興味はないけれど別に嫌いではない」というパターンが一番多いです。
このときは以下のような様子が見られます。
- お互いに顔を見合わせない
- 下を向いて地面の匂いを嗅ぎだす
- 地面の草を食べだす
- 背中を向けて座る
上記のような様子を見せながらも、その場にとどまり相手の犬から離れようとはしないときは、「はしゃぐほどの気分ではないけれどそばにいるのは嫌じゃない」という相性です。

決して相性が悪いわけではないですが、飼い主がそれ以上無理やり距離を縮めようとしないであげてください。
飼い主さん同士がお話をするあいだ、双方の愛犬は足元で大人しく待っていてくれるはずです。
気が合わなければ
気が合わない同士であったばあいは、犬同士に任せると以下のような反応が見られるでしょう。
- 一方の気が強すぎてもう一方が委縮
- 吠える
- 攻撃する(噛みつこうとする)
- 相手をにらむ(目をじっと見る)
このようなときは、それ以上触れ合わせず、今日のところは「バイバイ」をしましょう。
もし、気が合わない相手であったとしても、次に会ったときに無視をする必要はありません。
(相手の飼い主さんの理解と協力次第ですが)お互いに距離を縮めていけるように、その日のお互いの表情を観察しながら、徐々に挨拶に進めていけると良いですね。
ご近所の飼い主さんを教育してしまおう
反対にあなたが愛犬を保定して挨拶をさせている様子を見て、同じように愛犬を保定し愛犬のお尻の匂いを嗅がせてくれる飼い主さんもいます。
このときは、お礼を言ってこちらも相手のワンちゃんのお尻の匂いを嗅がせてもらいましょう。
犬同士の正しい挨拶の方法を知っている飼い主が増えれば、お散歩中にすれ違う犬たちと良いコミュニケーションが築ける環境をつくることができます。
犬の礼儀正しい挨拶のルールをどんどん広めて、自分たちの住む地域が愛犬と安心して暮らせる場所になったら嬉しいですね。
相手の犬に近づかせすぎない
ほかのワンちゃんの匂いを嗅ぐとき、相手のワンちゃんを気に入って、お尻に鼻をつけて匂いを嗅ごうとすることがあるかもしれません。
しかし、お尻をつつかれたほうの犬が攻撃を受けたと勘違いして、喧嘩に発展しないとも限りません。
「礼儀正しい挨拶」では相手の犬の身体に触れません。
もし、愛犬が匂いを嗅ぐ際に相手の犬に身体に触れそうな勢いのときは、身体や首輪をしっかり押さえて、前に出すぎて相手のお尻をつついてしまわないように距離を調整しましょう。
そして、あまりしつこくなりすぎないよう早めに切り上げさせます。
マウンティングさせない
また、「相手の犬が好きすぎる」「相手の犬と激しめの遊びをしたい」「俺の強さを見せつけてやろう」などの理由から、匂い嗅ぎの際に相手の犬の背中に乗っかって、マウンティングを始めてしまう犬もいます。
初対面の挨拶でマウンティングをするのはかなり失礼な行為です。
乗られた相手が真面目な性格の犬であれば、大きな喧嘩に発展してもおかしくありません。
- お互いに気が合い、
- マウンティングを含む少々荒っぽい遊び方を双方が好み、かつ、
- 相手の飼い主さんが許すのであれば、
2回目以降の挨拶からは、犬同士に任せてみても良いかもしれません。
しかし、最初は楽しく遊んでいたのにいつの間にか「ガチ喧嘩」になるのは、ヒトの幼児も犬も同じです。
飼い主は自分の犬の動向をつねに注視し、決して目を離してはいけません。

10秒ルール
相手のワンちゃんのことを気に入って、「もっと知りたい」という気持ちが高まると、いつまでも匂い嗅ぎを続けてしまいます。
しかし、我慢して待っている側からすれば、あまり長く待たされるとイライラしてしまいます。
嗅がれているほうの犬のイライラが高じて怒り出すと、喧嘩に発展してしまいかねません。
このため、どんなに相手のことが大好きでも、10秒以内に切り上げさせましょう。
犬同士の挨拶練習をする際のコツ
犬同士の挨拶をさせようとする際に、よくあるシチュエーションと、対処のコツをいくつかお伝えします。
匂いを嗅ぎたがらないときは…
シャイな性格やほかの犬とのかかわる経験が浅い犬は、匂いを嗅げといっても、なかなか近づこうとしないかもしれません。
ものすごーくマイペースな性格の犬も、ほかの犬にあまり興味がなく、匂いを嗅ぐという行動をしないかもしれません。
そんなときは愛犬を抱き上げて相手の犬のお尻の前にポンと優しく降ろしてあげます。
そして、このとき相手との距離感は必ず本人(犬)に選ばせてください。
今まで経験したことのない距離まで近づいたことで、興味を惹かれて匂いを嗅ぐかもしれませんし、すーっと離れてしまうかもしれません。
飼い主が少し手伝ってあげることで、興味をもってほかの犬のお尻の匂いを嗅げるようになると、ほかの犬とのかかわり方がどんどん上手になり、気の合うお友達もできますよ。
愛犬の好みを分析
犬はそれぞれ性格や好みが異なり、気の合う相手もいれば苦手な相手もいます。
飼い主は日々のお散歩で愛犬の挨拶を手伝いながら、愛犬の好みを分析します。
愛犬の得意・不得意の傾向が分かると、より良いコミュニケーションのサポートすることができます。
犬同士は「気」で相手を判断する
犬は見た目や大きさではなく「気(オーラ)」(≒匂い)で相手を判断します。
そのため、見た目の全く違う犬種同士でも気が合えば仲良くなれます。
犬種や大きさで判断しない
上記のとおり犬は相手を「気」で判断します。
身体の大きさで相手を判断しません。
小型犬だからといって決して「弱い」わけではありません。
小型犬に睨まれて震えあがる大型犬もたくさんいます。
カタチで判断している犬はメンタルが不安定
にもかかわらず相手の犬を判断する際に、身体の大きさや見た目で判断している犬が少なくありません。
感覚の8割を視覚に頼る人間との関わりが密になりすぎて、心が「犬らしさ」を失い精神的に不安定になっている犬は見た目で相手を判断しがちです。
もし、愛犬が犬を見た目で判断していたら、「鼻」を使って相手を知ることができていないと考えられます。
見た目で判断していると考えられるケース
以下のような行動をしがちな犬は、普段「鼻」を使っておらず見た目で相手を判断している傾向があると考えられます。
- 自分と見た目の大きく違う犬種に敵意をもつ
- 自分より大きい犬に対してよく吠える
- ほかの犬とお尻の匂いを嗅ぎあう挨拶ができない
精神的に安定している犬は相手の外見にとらわれず、匂いを基に相手を判断し堂々と接することができます。
お互いのお尻の匂いを嗅ぎあう「犬同士の礼儀正しい挨拶」を身につけさせることは、愛犬に心の安定をもたらします。
愛犬の好みの傾向を探る
匂い嗅ぎの様子を観察し、愛犬がどんなタイプの犬と気が合うのか傾向を探りましょう。
匂いを嗅ぐことから、犬たちは以下のような情報を手に入れています。
- 性格:遊び好きな犬、おとなしい犬など
- 年齢:子犬・成犬・老犬?
- 性別:オス・メスなど(未去勢・未避妊かも)
- 健康状態:内蔵や関節などに弱点があるか
苦手なのはどんなタイプ?
苦手なタイプの犬に共通する傾向には、どんなものがありますか?
- 性格:攻撃的、距離が近い、落ち着きがない、よく吠える、気が弱い
- 年齢:子犬、成犬(若年・中年)、老犬?
- 性別:オス・メスなど(未去勢・未避妊かも)
- 毛の色:黒い、自分と異なる毛色、単色、2~3色
- 毛質:自分の毛質と異なる(もじゃもじゃ、ふさふさ、つるつる)
- 形状:鼻ぺちゃ、足が短い・長い、耳が垂れている、しっぽがないなど
苦手なワンちゃんと遭遇したら?
苦手なタイプの傾向が分かってきたら愛犬が苦手そうな犬と出会ったとき飼い主はどうすればよいでしょうか。
飼い主は「ヨッシャ!ラッキー」と思うべし
飼い主が不安や緊張を感じれば愛犬も警戒します。
このため、苦手を克服する絶好のチャンスだと思って避けるのではなくチャレンジしていきましょう。
まとめ
多くの飼い主が自分の愛犬は「ビビり」だからほかの犬と触れ合わせないようにしなければいけないと勘違いをしています。

愛犬の可能性の芽を摘まないで
人間とともに暮らす「家庭犬」はほかの犬ともかかわって生活をしなければなりません。
苦手だからといって避けてばかりいると愛犬のストレス耐性はどんどん弱くなります。
また、飼い主も犬との暮らしをだんだん負担に感じて楽しくなくなってきてしまいます。
飼い主がビビりだと信じ込んでいる犬たちのほとんどはただ単に犬同士の挨拶ルールを知らず、経験が不足しているだけなのです。
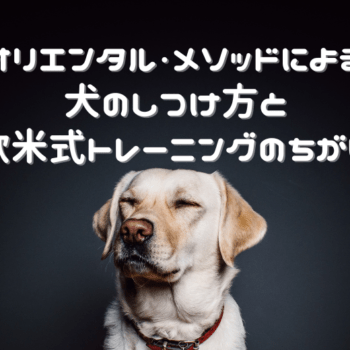
大人の振る舞いを身につけさせる
犬同士の挨拶はお散歩デビュー前から練習することが大切です。
ただし、子犬時代は上手にできていたとしても、思春期を経て上手にできなくなることがあります。
なぜなら、子ども用の挨拶と大人用の挨拶はちがうからです。
このため、子犬時代でしつけを終わりにせず、成長のステージに応じた内容で、練習を積み重ねる必要があります。

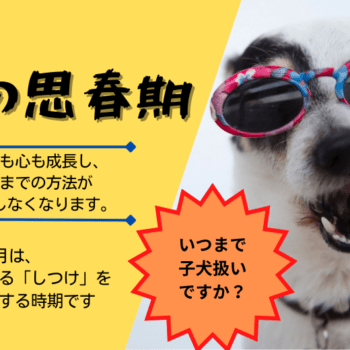
そして、犬同士の挨拶は必ずしも仲良くなるための儀式ではありません。
無用な争いを起こさないための儀式なのです。
もし、うまくいかなかったときは、喧嘩が起こるまえにすぐに引き離しましょう。
喧嘩になりそうな状況を察知できるよう、飼い主は犬のボディランゲージを読めるように学ぶ必要があります。
あなたにピッタリの情報かも?

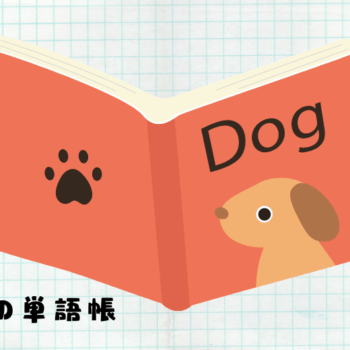

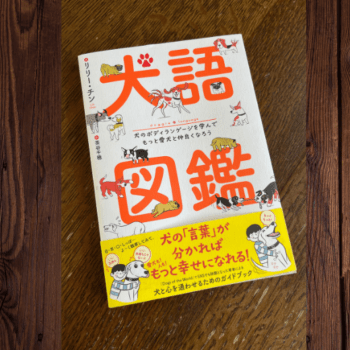
SuzyにLINEで質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。