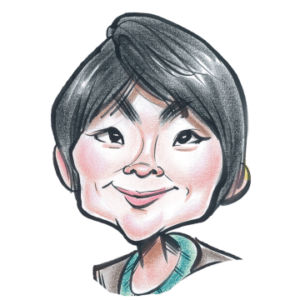犬の保護活動においては第一に保護犬の心身の健康状態を把握して必要な改善をしながら新しい家族との出会いを待つ準備をしていきます。
犬たちの飼い主募集を始める前に必要な医療措置を受けさせ、性格傾向や行動面の特徴を保護主が知っておくことで里親になる方も安心して迎えることができますし、犬たちも快適に新生活をスタートできます。
本記事では保護犬が飼い主募集の開始前に受ける一般的な医療措置について具体的な内容と目的を解説します。
健康診断
捕獲・保護された犬は保健所や保護施設に到着すると総合的な健康診断が行われます。
一般的な健康診断には体重測定、体温測定、血液検査、尿検査、糞便検査などが含まれます。
この段階で犬の健康状態や潜在的な病気、感染症の有無などを確認します。
伝染病や寄生虫が見つかったばあいはほかの犬や人間に感染しないようにすぐに治療が始まります。
こうした初期の健康診断は保護犬たちの全体的な健康状態を把握するために欠かせません。
血液検査
血液からはその犬の健康状態についてのさまざまな情報を得ることができます。
表面上は元気に見えても血液検査を行うことで初期段階の健康問題や、まだ症状が現れていない病気を発見できることがあります。
たとえば、腎臓や肝臓の機能異常、貧血、感染症などは血液検査によって判断をすることができ早期に治療につなげることが可能になります。
一口に血液検査といってもその項目は多岐にわたります。
例として宮古島で保健所に収容された犬たちが行なっている血液検査の検査項目を挙げます。
WBC(白血球数)
犬の白血球数(WBC: White Blood Cell count)は血液検査の重要な指標であり健康状態や体内での異常の有無を評価するための貴重な情報を提供します。
白血球は体内の免疫系において感染症や炎症と戦う重要な役割を果たしておりその数値はさまざまな要因で変動します。
犬の白血球数(WBC)は感染症、炎症、ストレス、免疫系の異常、骨髄の病気の兆候などさまざまな健康状態の評価に役立ちます。
WBCの数値だけでなく増減のパターンや他の血液成分とのバランスも合わせて考えることでより正確な診断と治療計画が立てられます。
以下は犬のWBCの値から分かる主な情報です。
感染症の有無(+)(-)
白血球数が増加している場合は身体が細菌やウイルス、寄生虫などの感染症と戦っている可能性があります。
細菌感染による増加はとくに顕著で身体が感染に対抗しようとして白血球を増やします。
また、ウイルス感染の場合は白血球数が一時的に減少することもあり増加していない場合でも異常な変動が見られることがあります。
炎症やアレルギー反応(+)
白血球数の上昇は感染症だけでなく体内の炎症やアレルギー反応が原因であることもあります。
たとえば、皮膚炎や関節炎、アレルギー反応が起こっていると白血球数が増えることがあります。
この増加は身体が異物や刺激物に対して免疫反応を引き起こしていることを示します。
ストレスの影響(+)
犬は強いストレスがかかると白血球数にも影響が出ることがあります。
とくに犬が緊張している、痛みを感じている、環境の変化にストレスを感じているといった場合に白血球数が一時的に上昇することがあります。
これは身体がストレスに対抗するために免疫系が活発化するために起こります。
免疫系の機能状態(-)
白血球数が非常に低い場合は免疫不全や免疫抑制が起きている可能性があります。
これは免疫力が低下している状態を示し感染症に対する抵抗力が弱くなるため健康リスクが高まります。
RBC(赤血球数)
犬の血液検査における赤血球数(RBC: Red Blood Cell count)は犬の健康状態や体内の酸素供給の状況を知るために重要な指標です。
赤血球の中にはヘモグロビンというタンパク質がありこれが酸素と結合することで酸素を体の隅々まで運ぶ役割を果たしています。
犬のRBC(赤血球数)は貧血や脱水、多血症、肺や心疾患、栄養状態、骨髄の健康状態など犬の全身の健康状態を把握するうえで重要な手がかりとなります。
RBCの数値とその増減パターンを分析することで体内での酸素供給の状態や潜在的な疾患の兆候を確認することができ早期に適切な治療を行うための指標として役立ちます。
以下は犬のRBCの値から分かる主な情報です。
貧血の有無(-)
赤血球数が低い場合は貧血の可能性が考えられます。
貧血は血液が十分な酸素を供給できない状態のことを指します。
貧血は犬が疲れやすくなったり元気がなくなったりする原因となります。
貧血の原因には出血、赤血球の生成不良(腎臓病や骨髄の異常など)、赤血球の破壊(自己免疫性疾患など)などがあり貧血の程度によってはさらに詳細な検査が必要になります。
脱水状態(+)
脱水が起こると血液が濃縮されて赤血球数が一時的に増加することがあります。
これは体内の水分量が減少しているため相対的に赤血球数が多く見えるからです。
犬は脱水状態にあると赤血球数だけでなく他の血液成分も異常を示すことが多く、症状としては元気の低下や食欲不振などが見られることがあります。
脱水が確認された場合は水分補給が重要となります。
酸素不足や肺疾患の兆候(+)
RBCが高い状態は犬が酸素をうまく取り込めていないことを示す場合もあります。
たとえば慢性の肺疾患や心疾患を抱えている犬では身体が酸素不足に適応しようとするために赤血球数が増加することがあります。
RBCの増加は肺や心臓に問題がある可能性を示唆しており、とくに呼吸が苦しそうであったり運動を嫌がるといった症状がみられる場合にはさらなる精密検査が推奨されます。
栄養状態やビタミンの影響(-)
赤血球の生成には鉄、ビタミンB12、葉酸といった栄養素が必要です。
栄養不足や吸収不良によりこれらの栄養素が欠乏するとRBCが減少し貧血を引き起こすことがあります。
また、慢性的な消化不良や腸の問題があるとビタミンや鉄分の吸収が不十分となり赤血球数が減少してしまうこともあります。
栄養状態が赤血球に与える影響は大きく食事の改善やサプリメントでの補助が必要になる場合があります。
HgB(ヘモグロビン濃度)
犬の血液検査におけるヘモグロビン濃度(HgB: Hemoglobin)は酸素を運搬する能力や体内での酸素供給状態を知るための重要な指標です。
ヘモグロビンは赤血球の中に存在し酸素を体中に運ぶ役割を担っているため、その値が増減することで犬の健康状態や潜在的な疾患の兆候が見えてきます。
犬のHgB(ヘモグロビン濃度)は体内の酸素供給状態や貧血、脱水、多血症、栄養状態、骨髄の健康状態を把握するために重要な指標です。
ヘモグロビン濃度の増減は体内で起きている問題や酸素供給の状態を反映しており犬の健康状態の早期発見に役立ちます。
以下は犬のHgBの値から分かる主な情報です。
貧血の有無とその原因(-)
ヘモグロビン濃度が低い場合、貧血の兆候である可能性があります。
貧血が起こると体内に十分な酸素が供給されず犬が疲れやすくなる、元気がなくなる、食欲が落ちるなどの症状が現れます。
貧血の原因はさまざまで以下のようなものがあります
出血性貧血
外傷や内出血、寄生虫などによる出血が原因でヘモグロビン濃度が下がります。
栄養不足性貧血
鉄分やビタミンB12、葉酸など赤血球やヘモグロビンの生成に必要な栄養素が不足している場合に発生します。
溶血性貧血
自己免疫疾患などによって赤血球が破壊されることでヘモグロビン濃度が低下します。
脱水状態の判断(+)
脱水が起きているときは血液が濃縮され相対的にヘモグロビン濃度が上がることがあります。
ヘモグロビン濃度が通常より高い場合は脱水の可能性が考えられます。
この場合ほかの血液成分と併せて確認することで脱水かどうかを判断できます。
脱水が原因であれば水分補給が改善策となります。
肺疾患や心疾患の可能性(+)
肺や心臓に問題がある場合、身体が酸素不足に適応しようとして赤血球やヘモグロビンを増やすことがあります。
このため慢性の肺疾患や心疾患のある犬ではヘモグロビン濃度が高くなることがあります。
とくに、運動を嫌がる、呼吸が荒い、唇や舌が青白く見えるといった症状がある場合は肺や心臓に異常がある可能性が高くさらに詳細な検査が必要です。
栄養状態やビタミン不足の影響(-)
ヘモグロビンの生成には鉄、ビタミンB12、葉酸といった栄養素が必要です。
これらが不足するとヘモグロビン濃度が低下してしまいます。
たとえば食事の栄養が偏っていたり消化吸収の問題でこれらの栄養素が十分に摂取できていない場合、犬のヘモグロビン濃度が下がり貧血の原因となります。
栄養状態を見直すことでヘモグロビン濃度を改善できる場合があります。
Hct(ヘマトクリット)
犬の血液検査におけるヘマトクリット(Hct: Hematocrit)は血液中に占める赤血球の割合を示す重要な指標です。
ヘマトクリット値は犬の全体的な健康状態や血液の濃度を把握するために役立ちます。
Hctが正常範囲にあることは血液循環が順調で酸素供給が適切に行われていることを示します。
この値が高すぎたり低すぎたりすることでさまざまな病状や体内の変化が分かります。
犬のHct(ヘマトクリット値)は貧血や脱水、多血症、栄養状態、血液量の変化など健康状態を包括的に評価するための重要な指標です。
Hctの異常な変動は酸素供給の問題や体内での異常な変化の兆候であり、ほかの血液検査の数値と併せて総合的に診断することで犬の健康状態をより詳しく把握することができます。
以下は犬のHctの値から分かる主な情報です。
貧血の有無(-)
ヘマトクリット値が低いときは貧血の可能性が高いと考えられます。
貧血になると身体の組織に十分な酸素が供給されなくなり犬が疲れやすくなったり、元気がなくなったりします。
貧血の原因としては以下のようなものが考えられます。
- 出血性貧血:外傷、内出血、寄生虫などによる血液の喪失
- 栄養不足性貧血:鉄分、ビタミンB12、葉酸といった栄養素の不足
- 溶血性貧血:自己免疫疾患などによる赤血球の破壊
貧血の原因が何かを特定するためにはさらに詳細な検査が必要です。
脱水状態の判断(+)
脱水状態になると血液が濃縮されてHctが上昇することがあります。
これは体内の水分が不足することで血液中の赤血球の割合が相対的に高くなるためです。
脱水状態であれば他の血液検査の値(たとえば血液の総タンパク質濃度)も上昇していることが多いです。
脱水が確認された場合はすぐに水分補給が必要です。
多血症(赤血球増加症)(+)
Hctが非常に高い場合、多血症または赤血球増加症が疑われます。
多血症は酸素不足を補うために赤血球が増加することで起こることがあり以下のような原因が考えられます。
慢性の酸素不足
高地で生活している犬や慢性の呼吸器疾患を抱える犬では身体が酸素不足に適応しようとして赤血球が増加しHctが高くなります。
心疾患や肺疾患
肺や心臓の異常が原因で十分な酸素が取り込めない場合にもHctが高くなることがあります。
骨髄の異常
赤血球を過剰に生成する疾患(赤血球増加症候群など)もHctの上昇につながります。
多血症は血液が粘性になり血栓ができやすくなるため適切な治療が必要になる場合があります。
栄養状態やビタミンの影響(-)
赤血球の生成には鉄、ビタミンB12、葉酸などの栄養素が必要でありこれらが不足するとHctが低下してしまうことがあります。
食事の栄養が偏っていたり吸収不良の問題があると赤血球の数が十分に確保できずHctが低くなる原因となります。
栄養補給や食事改善が必要となる場合があります。
血液量の変化(-)
大量の出血や手術の後は血液の総量が減少したことによってHctが低くなることがあります。
とくに急性の出血ではHct値が著しく減少するため輸血や治療が必要になることがあります。
急性の貧血は迅速な対応が求められます。
MCV(平均赤血球容積)
犬の血液検査におけるMCV(平均赤血球容積: Mean Corpuscular Volume)は赤血球の平均的な大きさを示す指標です。
MCVの値からは犬の貧血の種類や赤血球の生成に関する情報が得られ犬の体全体の健康状態を把握するための手がかりともなります。
犬のMCVは貧血の種類や原因を特定するために重要な指標であり鉄欠乏症やビタミン不足、肝臓疾患、甲状腺機能低下症、骨髄の異常など、さまざまな健康問題の兆候を把握することができます。
赤血球の大きさは酸素供給の効率や栄養状態を反映するためMCVの値とその変動から犬の健康状態を評価できます。
MCVが正常範囲から外れると赤血球に異常があることが考えられるためほかの血液検査の値や臨床症状も併せて状態を総合的に判断します。
以下は犬のMCVの値から分かる主な情報です。
貧血のタイプを特定
MCVの値は貧血の種類を特定するために役立ちます。
MCVが異常値である場合以下のように貧血のタイプを判断することができます。
小球性貧血(MCVが低い)
MCVが基準値より低い場合、小球性貧血の可能性があります。
小球性貧血は赤血球が通常よりも小さくなるタイプの貧血で主な原因には鉄欠乏症や慢性疾患が含まれます。
鉄分が不足すると赤血球の生成が不完全になり赤血球が小さくなる傾向があります。
大球性貧血(MCVが高い)
MCVが基準値より高い場合大球性貧血の可能性があります。
大球性貧血は赤血球が通常よりも大きくなるタイプの貧血でビタミンB12や葉酸の不足、あるいは骨髄の異常が原因となることが多いです。
とくにビタミン不足や肝臓疾患によって赤血球の成熟が遅れ大きく未成熟な赤血球が見られます。
正球性貧血(MCVが正常)
貧血の症状があるにもかかわらずMCVが正常値の場合は正球性貧血が疑われます。
これは出血や溶血(赤血球の破壊)などで急激に赤血球数が減少している状態です。
急性の出血や「免疫介在性溶血性貧血(IMHA)」などが原因として考えられます。
鉄欠乏症の診断(-)
MCVが低い場合は鉄欠乏症が疑われます。
鉄は赤血球の生成に必要不可欠な要素で鉄分が不足すると赤血球が小さくなりMCVも低下します。
鉄欠乏症の原因としては慢性的な出血(消化管内の出血や寄生虫感染など)や栄養不足が考えられます。
MCVが低いことに加え血清鉄やフェリチンの値を確認することで鉄欠乏症の確定診断が可能です。
ビタミン欠乏症の兆候(+)
MCVが高いときはビタミンB12や葉酸の不足が原因であることが多いです。
これらのビタミンは赤血球の生成や成熟に関わっており不足すると赤血球が異常に大きくなることがあります。
犬の食事や消化器系の問題によりビタミンの吸収が妨げられるとビタミン欠乏が起こりやすくなります。
食事内容を見直したりビタミン補充を行うことで改善が見込まれることがあります。
肝臓疾患や甲状腺機能低下症(+)
MCVの上昇は肝臓疾患や甲状腺機能低下症と関連している場合もあります。
肝臓疾患では赤血球の成熟が遅れるため大きな赤血球が増えMCVが高くなります。
また、甲状腺機能低下症でも赤血球生成が遅れることがありMCVが高くなることがあります。
これらの疾患はMCVだけでなく他の血液検査の値や臨床症状も総合的に考慮して診断が行われます。
骨髄の健康状態
MCVは骨髄の健康状態を知る手がかりともなります。
骨髄が正常に機能していない場合赤血球の大きさが変化することがあります。
とくに、骨髄の異常や白血病などの血液疾患では赤血球の生成に影響が出るためMCVに異常が見られることがあります。
このばあいMCVの異常に加えて赤血球形態の観察や骨髄検査が必要になることもあります。
MCH(平均赤血球ヘモグロビン量)
犬の血液検査におけるMCH(平均赤血球ヘモグロビン量: Mean Corpuscular Hemoglobin)は1つの赤血球に含まれるヘモグロビンの量を示す指標です。
MCHは赤血球の色調や酸素運搬能力を把握するために役立ちます。
たとえば貧血や栄養状態、さらには赤血球の生成に関連するさまざまな病態を把握する手がかりとなります。
MCHの値が基準値から外れている場合は貧血の種類や原因をより正確に特定するため、ほかの血液検査項目と併せて診断することが重要です。
以下は犬のMCHの値から分かる主な情報です。
貧血のタイプの判別
MCHは貧血の種類を特定するために役立つ指標です。
とくにMCHとMCV(平均赤血球容積)、MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)を合わせてみることで貧血のタイプや原因がより詳しく理解できます。
低色素性貧血(MCHが低い)
MCHが基準値より低い場合、低色素性貧血が疑われます。
これは赤血球1つあたりのヘモグロビン量が少ないことを示しており「鉄欠乏性貧血」が代表的な原因です。
鉄分が不足すると赤血球内でのヘモグロビン生成が不十分になり酸素の運搬能力が低下します。
高色素性貧血(MCHが高い)
MCHが基準値より高いばあい高色素性貧血が疑われます。
これは1つの赤血球あたりのヘモグロビン量が多いことを示しておりビタミンB12や葉酸の不足による「大球性貧血」が原因のことが多いです。
ビタミン不足や骨髄の異常があると赤血球が異常に大きくなりMCHも高くなる傾向があります。
鉄欠乏症の早期発見
MCHが低い場合は鉄欠乏症が疑われます。
とくに鉄はヘモグロビンの主要な構成要素であり鉄が不足すると赤血球内のヘモグロビン量も減少します。
これによりMCHが低下し酸素運搬能力が低下します。
慢性的な出血や寄生虫感染などで鉄欠乏が起こりやすいためMCHが低い場合は鉄の補充や原因の除去が必要になることがあります。
栄養状態の評価
MCHの値は栄養状態の把握にも役立ちます。
ビタミンB12や葉酸の不足があると赤血球が異常に大きくなりMCHが上昇することがあります。
ビタミン欠乏は食事内容や消化吸収機能に問題がある犬に見られやすいためMCHが高い場合はビタミン補充や食事の改善が検討されます。
赤血球生成の異常や骨髄の健康
MCHの値が基準値から外れるばあい赤血球生成に異常がある可能性も考えられます。
とくに骨髄で赤血球が正しく生成されないばあいMCHの値が異常になることがあります。
骨髄に異常があると赤血球の大きさやヘモグロビン量が不均一になり貧血が起こることもあります。
赤血球の形態と色調に関する情報
MCHは赤血球の色調(血液の色)にも影響を与えるためヘモグロビン量が低い場合は赤血球が淡く見え、高い場合は濃く見えます。
赤血球の色調が薄い場合は低色素性貧血、濃い場合は高色素性貧血が考えられます。
色調の変化は血液を顕微鏡で観察することで確認することができ貧血の種類を判断する手がかりとなります。
他の血液検査指標との関連
MCHはMCV(平均赤血球容積)やMCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)と一緒に評価されることでより詳細な健康状態を把握できます。
たとえば、MCVとMCHが両方とも高い場合は「大球性貧血」が疑われMCVとMCHが低い場合は「小球性貧血」が疑われます。
これらの数値を総合的にみることで犬の健康問題の原因やタイプをより正確に特定できます。
MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度)
犬の血液検査におけるMCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)は赤血球の中のヘモグロビン濃度を示す指標です。
MCHCは1リットルあたりの赤血球に含まれるヘモグロビンの割合を測定したもので赤血球の色調や酸素運搬能力の評価に役立ちます。
MCHCの値が基準範囲から外れている場合はほかの血液検査の項目と併せて診断し総合的に犬の健康状態を把握することが重要です。
以下は犬のMCHCの値から分かる主な情報です。
貧血の種類の判別
MCHCの値は貧血のタイプを判別するのに役立ちます。
ほかの指標(MCVやMCH)と併用することで貧血の原因や特徴をより正確に判断することができます。
低色素性貧血(MCHCが低い)
MCHCが基準値より低いばあい「低色素性貧血」が考えられます。
これは赤血球内のヘモグロビン濃度が低いことを示しており主に鉄欠乏症が原因です。
鉄が不足するとヘモグロビンの生成が不十分となり赤血球の酸素運搬能力が低下します。
このようなばあい血液が薄く赤血球の色が淡く見える傾向があります。
高色素性貧血(MCHCが高い)
MCHCが基準値より高いことは少ないですが赤血球の膜が異常に変形しているなど特定の疾患が関与している可能性があります。
たとえば、遺伝性球状赤血球症などの赤血球膜の異常によりMCHCが高くなることがあります。
鉄欠乏症の兆候
MCHCが低いばあい鉄欠乏性貧血が考えられます。
鉄はヘモグロビンの重要な構成要素であり鉄が不足すると赤血球内のヘモグロビン濃度が下がり酸素運搬能力も低下します。
鉄欠乏性貧血の原因としては慢性的な出血(寄生虫や内出血など)や栄養不足が挙げられます。
MCHCの低下とともに血清鉄やフェリチンの値を調べることで鉄欠乏の診断が確定されます。
赤血球の形態異常の把握
MCHCは赤血球の形態異常の有無を評価するのにも役立ちます。
とくに赤血球が異常に形状を変える病気(たとえば、遺伝性球状赤血球症や骨髄の異常)では赤血球内のヘモグロビン濃度が高くなることがあります。
これによりMCHCが基準値より高くなっていることで赤血球の破壊が促進される場合があります。
貧血の進行状況と改善傾向の把握
貧血の治療中にMCHCを測定することで治療の進行や貧血の改善状況を確認することができます。
たとえば、鉄剤やビタミンを補給している際にMCHCが正常範囲に戻ってくると赤血球内のヘモグロビン濃度が改善していることが分かります。
これにより治療方針の見直しや治療期間の延長が必要かどうかを判断する手助けとなります。
他の血液検査項目との関連性
MCHCは単独で評価するよりもMCV(平均赤血球容積)やMCH(平均赤血球ヘモグロビン量)と一緒に評価することで、より包括的な健康状態の把握が可能です。
たとえば、MCHCが低くMCVも低いばあいは「鉄欠乏性貧血」が疑われます。
しかし、MCHCが正常でMCVが高いばあいはビタミン欠乏による「大球性貧血」の可能性があります。
これらの数値を総合的に判断することで犬の貧血の原因やタイプを正確に診断できます。
赤血球の酸素運搬能力
MCHCの値は赤血球の酸素運搬能力を示す指標ともなります。
赤血球中のヘモグロビン濃度が適切であれば酸素を効率的に全身に運ぶことができ犬の活動能力や体力の維持に役立ちます。
したがって、MCHCが正常範囲内であれば赤血球の酸素運搬機能が適切に維持されていると考えられます。
PLT(血小板数)
犬の血液検査におけるPLT(血小板数: Platelet Count)は血液中の血小板の数を示す指標です。
血小板は血液の凝固に重要な役割を果たしており止血や血栓の形成をサポートします。
PLTの値が正常範囲から外れると出血傾向や血栓のリスクが高まる可能性がありさまざまな疾患や状態の兆候が分かります。
低いPLTは血小板減少症や出血傾向、骨髄機能の低下を示唆し高いPLTは慢性的な炎症や腫瘍、血栓のリスクを示唆する可能性があります。
PLTの値が異常なばあいはほかの血液検査結果や症状と合わせて診断することで犬の健康状態をより正確に把握することができます。
以下は犬のPLTの値から分かる主な情報です。
出血傾向や凝固異常の把握
PLTの値が低いばあい血液の凝固に問題があり出血傾向が高まる可能性があります。
血小板が少ないと傷口が塞がりにくく止血に時間がかかります。
出血の症状があるばあいPLTの数値を確認することで出血が血小板不足によるものかどうかを評価できます。
血小板減少症(PLTが低い)
PLTが基準値より低い状態を「血小板減少症」と呼びます。
血小板減少症の原因には免疫介在性血小板減少症(ITP)、マダニを起因とする感染症、中毒、骨髄の異常などがあります。
この状態では内出血や皮下出血が起こりやすくなります。
血小板増加症(PLTが高い)
PLTが基準値より高い場合は「血小板増加症」が疑われます。
血小板増加症の原因には慢性炎症、腫瘍、感染症、ストレス反応、特定の薬の副作用などが考えられます。
血小板が多すぎると血栓ができやすくなり血流障害の原因となることがあります。
感染症のサイン(-)
PLTの変動は感染症の兆候としても役立つばあいがあります。
たとえばバベシア症などの感染症では血小板が急激に減少することがあります。

ご注意本記事は獣医師ではないドッグトレーナーのSuzyが、さまざまな資料を基に記録したものです。ご自身の愛犬の治療や薬の選択の際はかかりつけの獣医師にご相談ください。 犬のバベシア症とは 犬の「バベシア症」とは赤血球内にバベシア原虫が寄生して貧血などの症状を引き起こす病気です。 原因はマダニに...
また、感染症に対する炎症反応が高まるとPLTが一時的に増加することもあります。
したがって、感染症が疑われる場合PLTの数値を確認し他の感染症関連指標と併せて評価することが重要です。
免疫疾患の可能性(-)
PLTの低下は「免疫介在性血小板減少症(ITP)」の可能性も考えられます。
ITPは犬の免疫システムが誤って自分の血小板を攻撃してしまう疾患です。
この病気により血小板が急激に減少し皮下出血や粘膜からの出血、血尿などの症状が現れることがあります。
骨髄機能の評価(-)
PLTの値は骨髄の機能も反映しています。
血小板は骨髄で生成されるためPLTが低いばあいは骨髄の機能低下が原因の可能性もあります。
とくに白血病や骨髄腫瘍あるいは重度の貧血などが原因で骨髄の機能が低下すると血小板数が減少することがあります。
このようなばあいPLTだけでなく白血球数や赤血球数などの他の血液検査結果も確認して総合的に判断します。
炎症や腫瘍の存在(+)
PLTが高いばあい体内で炎症が起こっている可能性もあります。
慢性的な炎症や一部の腫瘍(たとえば血小板生成を促進する腫瘍)により血小板数が増加することがあります。
また、慢性疾患や免疫反応が続くと血小板の数が一時的に上昇することがあります。
したがって、PLTの上昇は必ずしも病気の直接的な証拠ではないため臨床症状や他の血液検査結果と併せて評価します。
RETIC(網状赤血球)
犬の血液検査におけるReticulocytes: RETIC(網状赤血球:レチクロ)値は主に骨髄の赤血球生成機能を評価するために使われます。
網状赤血球とは新しい赤血球(未成熟な赤血球)のことをいいます。
網状赤血球は犬の骨髄で新しく作られ数日かけて成熟します。
RETIC値を測定することで犬が十分な赤血球を生成しているかどうかや貧血などの問題があるばあいに骨髄がそれに応じて反応しているかどうかを把握できます。
具体的にはRETIC値から以下のようなことが分かります。
再生性貧血(+)
網状赤血球の数が増加しているばあいは身体が貧血に対して反応し新しい赤血球を作ろうとしている可能性があります。
これは「再生性貧血」と呼ばれ血液の失血や破壊が原因で発生することがあります。
非再生性貧血(-)
反対に貧血があるにもかかわらず網状赤血球の数が増えていない場合は「非再生性貧血」が考えられます。
これは骨髄の問題や赤血球の生成が何らかの理由で抑制されている場合に見られます。
骨髄の健康状態(-)
RETIC値は骨髄が正常に働いているかどうかを示す指標にもなります。
何らかの病気やストレス、栄養不足、または薬物の影響で骨髄機能が低下しているとRETIC値が低下することがあります。
CHW(犬糸状虫症)
犬の血液検査におけるCHWはCanine Heartworm(犬糸状虫症)の略で犬糸状虫(フィラリア)感染の有無を検査するための項目です。
犬糸状虫は犬の心臓や肺の血管に寄生し重篤な症状を引き起こす寄生虫です。
犬糸状虫症は蚊を媒介して感染するためとくに予防が重要です。
CHW検査の結果は主に次のような情報を提供します。
フィラリア感染の有無
CHW検査の結果が陽性のばあい犬がフィラリアに感染していることを示します。
成虫が循環器に寄生して繁殖している可能性があります。
感染の段階
CHW検査によって感染初期か感染が進行しているかをある程度判断できます。
感染の進行度に応じて治療方法が異なるためフィラリア抗原検査などと併用して、より詳細な診断が行われることが多いです。
CHW検査結果に基づく対応
検査結果によって対応方法が異なります。
陽性の場合
感染が発覚したら進行具合によっては寄生虫が心臓や肺に影響を及ぼしている可能性があるため超音波検査やレントゲン検査で臓器の状態を評価することが一般的です。
これにより治療方法を決定し感染した寄生虫の駆除を行います。

南国の宮古島からやってくる保護犬たちは、残念なことに保護時にはすでにフィラリア症になっていることが少なくありません。犬を飼うなら「フィラリアは必ず予防しなければならないもの」ということは知っていましたが「すでにフィラリア陽性になっている犬を迎えたらどうすれば良いのか」ということはタラ氏を迎え...
陰性の場合
フィラリア感染がない(陰性)と判断されても予防薬を適切に継続していくことが必要です。
.png)
毎月、愛犬に与えている「フィラリア予防薬」には、さまざまな種類があります。しかし、獣医さんに処方されたお薬を言われるままに投与していて内容のちがいについて気にしたことがない飼い主さんも少なくないことでしょう。かかりつけ以外の動物病院に行った際に、どのフィラリア予防薬を使っているのか聞...
気候変動により気温の高い期間が長くなった日本においては通年の予防が望ましくなりつつあります。
CHW検査は犬の健康管理において重要な検査の一つです。
フィラリア感染は予防が可能ですが重症化すると治療が困難な場合があるため定期的な検査と予防が不可欠です。
ワクチン接種
つぎに、必要な2つのワクチン接種が行われます。
ひとつは「狂犬病ワクチン」もう一つは各種の伝染病に対する「混合ワクチン」です。
これらのワクチンはとくに保護施設など多くの犬が集まる環境で生活するばあいに不可欠です。
ワクチンを接種することで犬自身が病気にかかるリスクを軽減するだけでなく施設内で他の犬への感染が広がるのを防ぐ効果もあります。
狂犬病ワクチン
「狂犬病予防法」で1年に1回の接種が義務付けられています。
狂犬病は人も感染する「人獣共通感染症」で発症すれば治療法がありません。
狂犬病については以下の記事で詳しく解説しています。
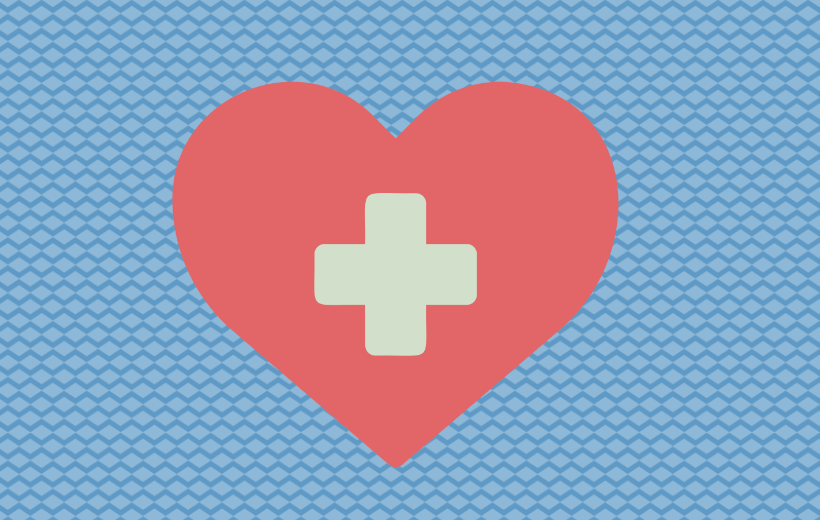
犬の飼い主には、毎年1回の狂犬病ワクチンの接種が「狂犬病予防法」で義務づけられています。しかしながら、日本国内での狂犬病の発生がみられなくなって久しいことから、動物を商売にしている人でさえ、狂犬病の恐ろしさを知らない人が少なくありません。世界では、いまだ年間に5万人近い人がこの病気に...
混合ワクチン
法律では定められていないものの「犬から犬」もしくは「犬から人」に感染する(比較的重篤な)感染症の蔓延を防ぐための予防接種があり一般的に「混合ワクチン」として接種します。
混合ワクチンは複数の病気に効果的なワクチンを組み合わせてまとめて一度に接種するものです。
その組み合わせによって2種混合から11種混合まで種類があります。
5~6種のワクチンを接種されることが多いです。
コアワクチン
致死率の高い感染症を防ぐためにすべての犬に接種するように勧告されているワクチンを「コアワクチン」といいます。
- 犬ジステンパー
- 犬伝染性肝炎
- 犬アデノウィルス(II型)感染症
- 犬パルボウイルス感染症
ノンコアワクチン
住んでいる地域によって発生状況が異なる感染症は接種することが推奨される種類が異なるため「ノンコアワクチン」と分類されています。
追加するワクチンの種類が増えるほどワクチンの値段が高くなります。
- 犬パラインフルエンザ
- 犬コロナウイルス感染症
- レプトスピラ症(イクテロヘモラジー型)
- レプトスピラ症(カニコーラ型)
寄生虫駆除
保護犬の多くは保護される前に外部寄生虫・内部寄生虫に感染していることが珍しくありません。
そのため保護後にすぐノミやダニなどの外部寄生虫の駆除を行ない内部寄生虫に対しては駆虫薬が投与されます。
内部寄生虫の駆除・予防
内部寄生虫とはいわゆる「お腹の虫」で腸に寄生して宿主の栄養を奪う寄生虫です。
糞便などを経由した経口感染が多く子犬など体力や免疫力の落ちた犬では命の危険が及ぶことも少なくありません。
種類によっては犬から人へ感染して重篤な症状を生じる寄生虫も存在します。
寄生虫の種類と駆虫薬についてのより詳しい内容は以下のページで解説しています。

野犬や飼育放棄(ネグレクト)、ブリーダー崩壊など、適切な健康管理がなされず衛生的でない環境で生きてきた犬たちは、日ごろから予防医療がきちんとなされている家庭犬たちがもっていない感染症に罹患していることがあります。犬の3大感染症 これらの犬たちが感染することの多い感染症は大きく分けて以下...
外部寄生虫の駆除・予防
外部寄生虫とは身体の外側に棲みつこうとする節足動物のことでノミやマダニが犬のおもな外部寄生虫です。
身体の外側から吸血するときに犬の血管内に寄生虫が移動しバベシア症、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)など重篤な病気の発生原因となります。
外部寄生虫の駆虫については以下の記事で詳しく解説しています。

ご注意本記事は獣医師ではないドッグトレーナーのSuzyが、さまざまな資料を基に記録したものです。ご自身の愛犬の治療や薬の選択の際はかかりつけの獣医師にご相談ください。 犬のバベシア症とは 犬の「バベシア症」とは赤血球内にバベシア原虫が寄生して貧血などの症状を引き起こす病気です。 原因はマダニに...
避妊・去勢手術
多くの保護施設では犬の避妊・去勢手術も重要な医療措置として行っています。
譲渡前に繁殖防止措置を済ませておくことで望まれない子犬が増えるのを防ぎ、長期的な視点に立ってみれば保護しなければならない新たな犬の数を減少させることができるからです。
また、避妊・去勢手術は将来的な子宮や精巣の病気、特定のがんリスクの低減、攻撃性や徘徊行動の軽減にも効果があるとされています。
避妊・去勢手術は犬の健康と行動の安定性を高める重要な措置の一つです。
メンタルケア
さいごに犬が新しい環境に適応できるよう精神面のケアやリハビリテーションが行われることもあります。
保護犬の多くは過去に虐待やネグレクトを受けていたりするなど人への不信感や特定の状況に対するトラウマを抱えていたりします。
こうした犬に対して専門のトレーナーや経験豊富なボランティアスタッフが適切な環境を与え、トレーニングを通じて人への信頼感を育みながら新しい生活に慣れやすくなるようサポートを行います。
メンタルケアは身体の健康と同じく非常に重要です。
人間や新しい環境に対して過敏な状態のまま新しい飼い主の元へ移っても、家庭犬として馴染めるようになる前に脱走して命を失ってしまったり、扱いに困った飼い主に再び捨てられたりネグレクトを受けることにつながるからです。
まとめ
以上のように保護犬が里親募集開始までに受ける心身のケアは多岐にわたります。
総合的な健康診断やワクチン接種、寄生虫駆除、避妊・去勢手術、そしてメンタルケアを含む一連の処置が実施されることで犬たちはより健康的で安定した状態で新しい家族のもとに送り出されます。
これらの医療措置は犬たちが新しい環境で幸せな生活を始めるための重要なステップであり、同時に里親になる方にも安心感を提供するものです。
保護犬が新しい生活に移る前には多くの費用を掛けてさまざまな医療ケアを受けています。
こうした費用が多くの方々の支援があって成り立っていることを知って欲しいと思います。

テレビやSNSで飼い主のいない犬たちの情報をたくさん目にするようになりました。日々、そうした犬たちの映像を目の当たりにして、これまでは「どこか遠くで起こっているのかもしれない」と思っていたことが「現実に身近で起きていること」として突き付けられます。この記事を読んでいる方のなかには、こ...
関連記事
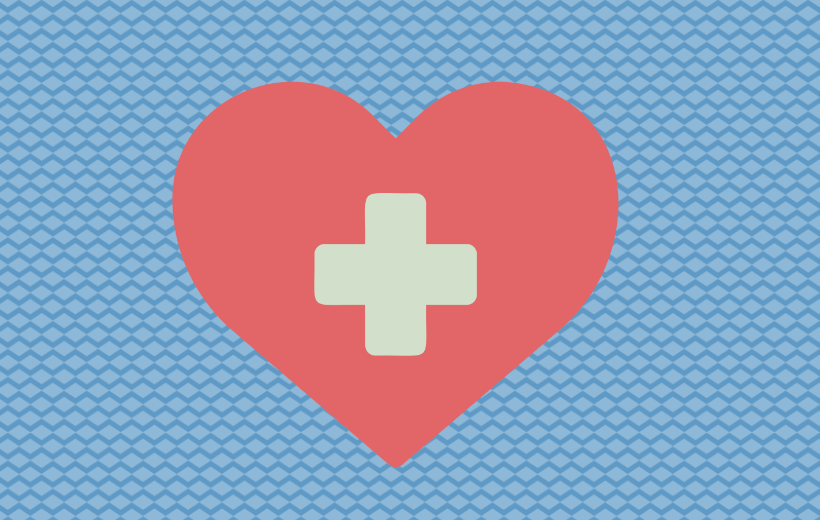
犬の飼い主には、毎年1回の狂犬病ワクチンの接種が「狂犬病予防法」で義務づけられています。しかしながら、日本国内での狂犬病の発生がみられなくなって久しいことから、動物を商売にしている人でさえ、狂犬病の恐ろしさを知らない人が少なくありません。世界では、いまだ年間に5万人近い人がこの病気に...

ご注意本記事は獣医師ではないドッグトレーナーのSuzyが、さまざまな資料を基に記録したものです。ご自身の愛犬の治療や薬の選択の際はかかりつけの獣医師にご相談ください。 犬のバベシア症とは 犬の「バベシア症」とは赤血球内にバベシア原虫が寄生して貧血などの症状を引き起こす病気です。 原因はマダニに...

野犬や飼育放棄(ネグレクト)、ブリーダー崩壊など、適切な健康管理がなされず衛生的でない環境で生きてきた犬たちは、日ごろから予防医療がきちんとなされている家庭犬たちがもっていない感染症に罹患していることがあります。犬の3大感染症 これらの犬たちが感染することの多い感染症は大きく分けて以下...

南国の宮古島からやってくる保護犬たちは、残念なことに保護時にはすでにフィラリア症になっていることが少なくありません。犬を飼うなら「フィラリアは必ず予防しなければならないもの」ということは知っていましたが「すでにフィラリア陽性になっている犬を迎えたらどうすれば良いのか」ということはタラ氏を迎え...
LINEでSuzyに質問!
この記事を読んでもっと知りたいことや疑問が沸いてきたら、以下のページからLINEのお友達登録のうえチャットでSuzyにご質問ください。
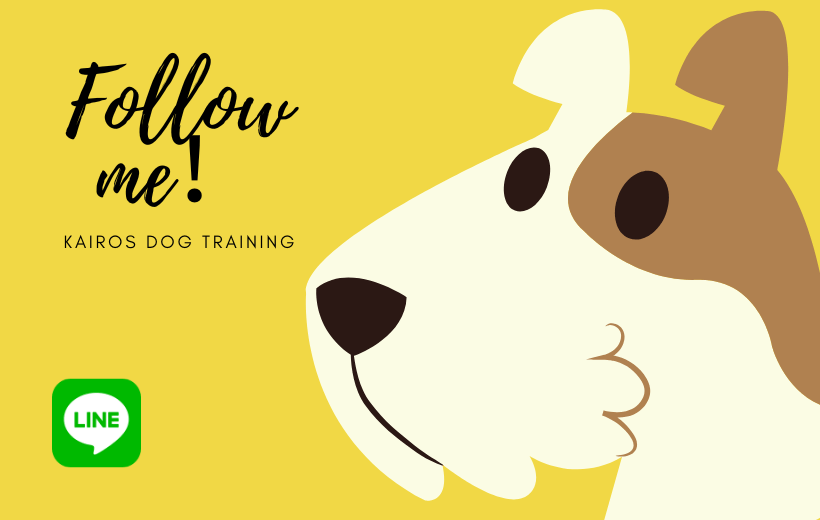
Suzyに聞きたい! 犬のしつけ情報を探してインターネットをしていてこのサイトにたどり着き、いろいろな記事を読んでみて、もっと知りたいと思うことがあったかもしれません。そんなときは、LINEお友達登録のうえ、チャットでご質問をお送りください。 質問受付中 誰かが知りたいと思っていること...